【経営革新コラム】 儲かるキラーサービスをつくる社長の視点 第170話:価格が上げられないたったひとつの理由
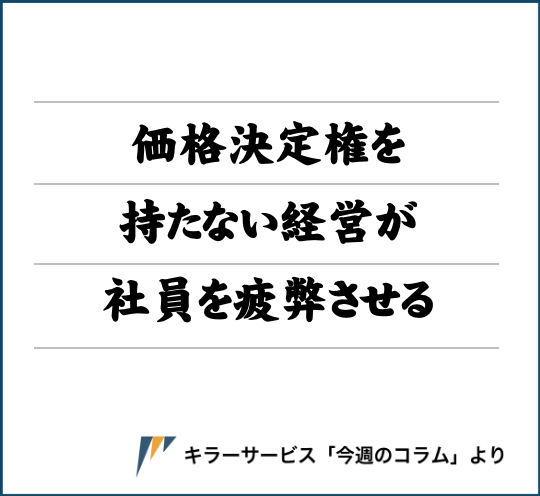
「小回りをきかせるというのが当社の強みと思っていました…」── 金属加工業を営むR社の社長の言葉です。
中小企業は当然ながら大企業に比べてリソースで劣ります。ヒトモノカネが潤沢にありません。中小が大企業とガチンコの戦い方をしてしまってはひとたまりもありません。
弱者は弱者なりの戦い方をする必要があります。しかしながら、多くの中小企業が「間違った弱者の戦い方」を選択します。そのひとつが、冒頭の「小回りをきかせる」というものです。
超小ロット・短納期で納入したり、細かな設計や仕様の変更に応えたり、特別な納入形態に対応したりと、顧客からのさまざまな個別対応のリクエストに応じます。
「それの何が悪いんだ。顧客が喜ぶんだからいいじゃないか!」と思われるかもしれませんが、問題はそういった対応をしても単価が余分に取れないということです。そして、「むちゃくちゃ忙しいのに全然儲からない」という状態に多くの中小企業が陥ってしまっているのです。
「顧客の要望に100%応える」 一見良いことのように思いますが、これが自社を下請け化させることになります。そして得られる報酬は「作業代金」となってしまい、自社が価格のコントロール権を握ることができなくなります。
なぜ価格決定権を握れないか…その理由は単純で、顧客の要望に応えるだけでは「自社ならではの企画・提案」がないからです。仕事が「知恵を絞る」部分と「手を動かす」部分に分かれるとすると、知恵を絞っているのは顧客の側となるため、こちらで価格が決められないのです。
「作業代だけを取りに行かない」― ここが中小企業経営の非常に重要なポイントです。顧客が喜ぶ「知恵」は自社の中に必ずあります。それを見える化・体系化することで商売の幅や奥行きをぐっと広げることができるのです。
実はこのコロナ禍において、このように「知恵」を売っているかどうかが大きく明暗を分ける要素となっています。
「モノからコトへ」と言われて久しいですが、これの言っているところは、商品を提供するだけでは顧客は満足しないですよ、もっと「コト」、つまり体験を提供しないと駄目ですよ、ということです。
しかしながら、コロナで「体験」に制限がかかりました。人が集まる形でのイベントなどを催すことができなくなったり、やったとしても人が集まらなかったり…。代わりに人が自宅などで「コト」を楽しむ風潮に変わってきています。
そこで必要になるのが「知恵」です。自分たちで楽しむために、オンラインなどでやり方やノウハウを知りたい、あるいは指導してもらいたい、といったニーズが生まれています。
その「知恵」をうまく顧客に届けているところはいま非常に売れています。逆にこのポイントを押さえずに、単に今までの商品やサービスの提供をオンライン化・通販化しただけのところは苦労しています。それは当然で、同じような商品・サービスがすでにオンラインで他から手に入るからです。
これはもちろんB to B(対企業)のビジネスでも同じことです。いまのような時代が大きく変わる局面においては、単なる商品や、あるいは前述したような「作業代行」ではなく、自分たちのビジネスを飛躍させるための「知恵」が求められることになります。いわばそういった無形のものを「モノ化」して提供できるかどうかが非常に大事になってきます。
この「モノ化」を別な表現で表すと、当社が常に提唱している「サービスの標準化」となります。顧客に対する「プラスアルファ」の手助けを事前に体系化しパッケージ化することで、非常に売りやすく、また提供する際も非常に効率的に進めることができます。
たとえば当社のコンサルティングも全10回のステップがあり、事前に体系化・標準化されています。これにそってコンサルティングを進めることで、顧客の社内に仕組みが作られることになります。この標準化がなければ、顧客のところに伺う度に「お悩み相談」のようになってしまい、対処療法的なアプローチになってしまうことでしょう。
いっとき多くの企業が「コンサルティング営業」を提唱したものの、結局営業マンが究極の「御用聞き営業」と化して顧客に振り回された…というのも、事前の体系化・標準化ができていかなかったことが原因です。
もちろんコンサルティングに限らず、顧客に「プラスアルファ」のサポートを提供するのであれば、この「モノ化」「標準化」をいうアプローチは必須となります。それにより自社ならではの「企画・提案」を持つことができるのです。
顧客はこれまで以上に深い関わりを求めています。単に商品やサービスを提供して終わり、というのでは商売が成り立たなくなっています。顧客との関わり方を見直すことでビジネスを「大化け」させる── その絶好の機会が来ているのです。
御社は自社が持つ無形の「知恵」を売れるカタチに転換できていますか?
従来の「モノ売り」の発想のまま、安易なオンライン化・通販化に進んでいませんか?
顧客との関わり方を進化(深化)させ、顧客に大きく貢献しつつ価格決定権を握れる事業をつくっていきましょう。
