【経営革新コラム】 儲かるキラーサービスをつくる社長の視点 第196話:差別化できているのに業績が上がらない理由
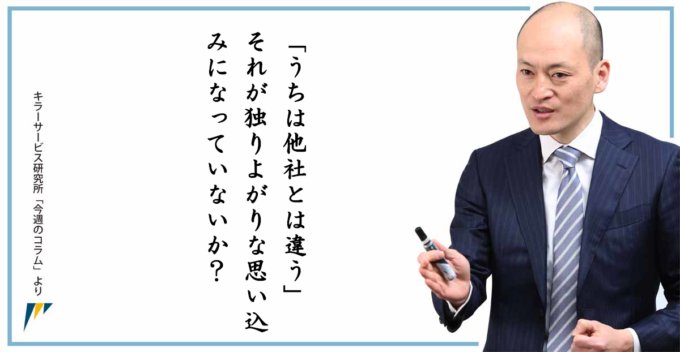
「うちはかなりよそとの差別化をやってきたんで、おもしろい事業になってると思うんですけど、結果が出てないんですよねえ…」― 先日、当社のセミナーをご受講いただいた経営者が噛みしめるようにそうおっしゃいました。
代替わりをされてトップに就任して依頼、他社とは一線を画すサービスを提供してきたが、業績は思うように上がっていないとのこと。
何事も結果の数字だけでは到底表せられない何か大事なことがあるとしても、ビジネスではやはり結果を数字で出さないといけない。その結果がついてきていないことに対してとてももどかしくお感じになっている様子でした。
他社とは差別化できているのに、なぜ結果が出ないのか? その理由については複数考えられるものの、何かが噛み合っていないのは確かでしょう。
それが何かを経営者が正確に把握できていないと、当然ですが戦略が本来やるべきこととずれてしまいます。
ここで、まず見るべきは粗利率です。他社と差別化された強い事業というのは業界平均を大きく上回る粗利率を叩き出します。つまり、低価格で勝負していないということの現れです。
もし、自社の事業は差別化になっていると思っていても、この粗利率が低いままという場合は、その原因の可能性は3つあります。
まずひとつ目は、「顧客から見て本当の差別化になっていない」というものです。差別化できていると思っているのは自分たちだけで、肝心のお客様の方は他社とよく似たものだと思っているパターンですが、これは本当によくあります。
品質ははるかにこちらの方がいいんだ。
商品の使い勝手ではうちのが一番だ。
他社よりも顧客のためになる提案をしている。
納期ではどこにも負けていない…。
こういうことをいくら思っていても、お客様の方では「いやいや、もっとはっきりした「差」を見せてくれないと」と思って価格差を求めてくる。
この場合はやはり、相手(顧客)にとって確かに他と違うと思える形に商売を変える必要があります。ライバルと同じ戦い方で競り勝とうとするのではなく、全く違う切り口で戦う(=誰とも戦わない)ことが重要です。
当社のコンサルティングでもここにこだわっていて、とにかく相見積もりにならない事業の構築をお手伝いしています。値段ではなくて価値で選んでほしい…経営者なら誰しもが願うことです。
そして、粗利率が低い原因のふたつ目としては、「相場で売らないといけないと思い込んでいる」ということです。
実は差別化ができていて価格で勝負しなくてもいいのに、やっぱり他社と同等の価格にしないと怖い。お客様のためと言いながら、実は昔から抱えている「安売りマインド」が捨てきれないというパターンです。
その背景には往々にして「みんなに好かれたい」という考えがベースにあったりします。価格を上げてしまうと価格にシビアなお客様を逃してしまうことを恐れてのことです。
しかし、ビジネスで肝心なことは、本当に相手にすべきお客様に選ばれることです。自社の戦略として低価格層もしっかり取り込もう!というのではれば話は別ですが、ちゃんと(価格以外の)価値を認めてくれる顧客を相手にしようと考えているならば、むしろ価格はしっかり値づけしないと他と同じものと思われてしまいます。
例えば私も愛用しているバルミューダのトースター。出荷台数が累計100万台超えというヒット商品で、価格はトースターとしては異例の2万円超えですが、これが数千円で売られていたら台数自体もここまで伸びていなかったのではないでしょうか。桁違いの価格が他社品との確かな「違い」の証明になっているということです。
安売りマインドでは意識がコスト面ばかりに向かいます。「安くするためにはどうしたらいいか」とばかり考えるということです。もちろん、コストを下げることは重要ですが、値段で勝負する商売というのはよほどのスケールメリットがないと絶対に成り立たない(=中小企業が選択する道ではない)ということは肝に命じる必要があるでしょう。
そして、粗利率が低い原因の3つめ。安売りしていないし、ちゃんと売れてもいるが粗利率は低いというパターンであれば、これはやはり「必要以上のコストがかかっている」ということになるでしょう。差別化するために他社ではやらないイレギュラーなことをやっているために、コストも同じようにかかってしまっているというパターンです。
ここで大事なことは、「外から見たらイレギュラー、でも中から見たらレギュラー」つまり業務を標準化して、顧客からしたら特別なことであっても自分たちは通常業務で回せるように仕組み化するということです。
超高収益起業として有名なキーエンスは、「絶対特注はつくらない」というポリシーがあります。なぜなら手間ばかりかかって儲からないからです。その代わり、ユニークな自社商品の組み合わせで顧客に対して独自の提案を実現しています。
かつて私が勤めたミスミでも、特注の見積もりは相場の3倍ぐらいの値段で返しています。特注は端から取る気がないということです。そうやって高い価格を出すと同時にミスミ標準品を提案してそちらに誘導しています。
特注ではなくて「半特注」、ガチガチの標準ではなくて「半標準」。この絶妙なバランスで顧客のニーズに合わせた商品・サービスを提供することが、儲かる商売を実現するための要諦であり、かつ顧客にとっても一番メリットが出る形となります。
そのうえで、業務オペレーションもできるだけ仕組み化・標準化してイレギュラーをなくしていくと、同じことを実現するのに必要な仕事の工数を大きく減らすことができるはずです。
以上、差別化できているはずなのに業績(利益率)が良くならない企業で起こっているであろうことを論じてみました。大事なことは、いま自社事業の何が問題かを正確に把握することです。その上で適切な手を打っていけば結果は必ずついてきます。
御社は自社独自の価値を利益に変えることができていますか?
価格勝負ではなく価値勝負で顧客に選ばれる企業を目指していきましょう。
