【経営革新コラム】 儲かるキラーサービスをつくる社長の視点 第201話:新規事業を考えるときにやってはいけないこと
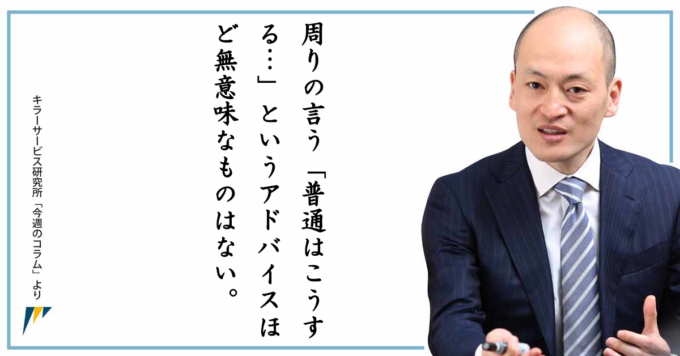
「開業融資を受けるのに自分のビジネスを説明したんですが、駄目出しされて大変でしたよ」― お知り合いの女性経営者の方と話していたときに、ふとそんな話題が出ました。
なんでも、その融資を受けるためには、事前に中小企業診断士のアドバイスを受ける必要があるらしく、その方にいろいろと駄目出しされて往生したんだとか。
その方のビジネスはなかなかユニークで、体の不調を抱える人に対して自宅マンションにて温熱治療を施し、そのあとは薬膳料理をお出しして、一緒に食事をしながら健康に関するご助言なんかもして…という感じで、お客様にとてもゆったりとした時間を過ごしていただくというもの。
私もプレオープンの際に伺ったのですが、とてもかわった温熱治療で全身がポカポカになり、すっかり体が緩んで眠ってしまいました。そして料理もめちゃくちゃおいしく、さらに健康法に関するアドバイスも適切というか聞いてるだけで楽しいもので、ものすごく有意義でリラックスした時間を過ごすことができました。
看板も出ていませんし、実際に受けたことのあるお客様の紹介しか受けつけていないとのことで、会員制の秘密クラブさながらの「知る人ぞ知る」サービスとなっていますが、これは放っておいてもお客様が口コミで広めていくだろうという気がします。(現に私はすでに何人もの友人に紹介しました。笑)
話しを元にもどすと、その中小企業診断士の方に言われたのは、
「施術サロンというのは普通は店舗を借りるもの」
「店舗ビジネスでは看板が大事!」
「施術サロンで普通食事は出さない」
「あなたも一緒に食事をするっていうのはおかしい!」
「ちゃんとホームページで宣伝しないと新規が増えない」
「人を雇わないとビジネスが大きくならない」
などといった、アドバイス(?)のオンパレードだったとか…。
特に「ちゃんと看板は出しなさい」としつこかったらしいのですが、銀行お抱えの中小企業診断士レベルといったら失礼ですが、そういう方は看板のない隠れ家レストランなんぞには行ったことがないんだろうなあ…としみじみ思った次第です。
私は「特別ビジネスづくり」をお手伝いしているぐらいですから、看板もないような「変なお店」は昔から大好きで、いきつけの料理屋やバーに看板のないところは多いですし、スーツをつくってもらっているところも看板の出ていないマンションの一室でやられています。
また、当コラムやセミナーでもちょくちょく話題にしている行きつけの床屋は、「普通」ではないサービスメニューがたくさんあって顧客単価は1万円を超えていますし、関わらせていただいているクライアント先に対しても常に「普通」ではない事業コンセプトづくりをご支援しています。
「普通はこうだ…」といって「自分の普通」を他人にまで押しつけてくる人がとにかく多いわけですが、ビジネスの世界で経営者がそんな同調圧力の声に耳を傾けていたら事業はとんでもないことになってしまいます。
事業をやるうえで経営者が手を出してはいけないものが2つあります。そのひとつが「普通」であり、もうひとつは「流行」です。
「普通」に手を出してはいけない理由は明確です。「普通」と言われるものは必然的に「低価格」になってしまうからです。
定番品を安く売る商売というのは、基本的には大手企業でないと取れない戦略です。大手なら数が見込めますから、製造や調達コストが中小に比べて安くすみます。また、すでにブランドが確立していますし、他の商品の連れ買いも起こりやすいですから、追加的な販売コストも低いです。
それに比べて中小の場合は、新しい商品やサービスを立ち上げる際のコストが高いですから、低価格の商売をやっても「貧乏暇なし」、つまり売上は立っても利益が出ないということになりがちです。
中小企業の採るべき戦略は、基本的には「高価格戦略」しかないのです。
また、「流行」に手を出すのはもっと危険です。なぜなら、流行ったものはすぐにすたれるからです。
もちろん、どんな商品やサービスにも寿命はあります。プロダクトライフサイクルというやつです。しかしながら、一気に流行ったものはすたれるのも本当に急です。
最近ですと、タピオカとか鬼滅の刃なんかがそうです。流行る勢いもすごかったですが、冷めるのも一気でした。
いま流行っているものと言ったら「フルーツサンド」でしょうか。先日締め切られた事業再構築補助金でも、フルーツサンド販売店の開業という申請内容が非常に多かったといいます。
ひどいことに、フルーツサンド事業でまったく同じ文面で数社の事業計画をだしまくった税理士事務所もあるそうで、業界では「フルーツサンド税理士法人」と呼ばれているそうなのですが(笑)、それこそ普通に考えたらフルーツサンドなどタピオカの二の舞になるのは明白です。
これが消費者の立場なら、「なんかいつのまにかブームが去ったな…」てな感じで大した話ではないのですが、それを提供する側の経営者からしたら死活問題といいますか、もう「死」しかないわけで、そんな流行りものに手を出すことは、もはや経営ではなくて博打レベルの話になってしまいます。
何が言いたいのかといいますと、数を狙って目の前に見えているわかりやすいものに飛びついても駄目だということです。
いますでに他の企業が提供していることを真似して市場参入することなど、商売として筋が悪いだけでなく、そんなことをやっておもしろいですか?という単純な疑問を持ちます。なんの意味があるんですか?という話です。
ソニーのウォークマンの例を持ち出すまでもなく、世にないものを出そうとすると社員が反対するというのはよくある話です。ニトリの会長も「社員に反対されたものほど、やる」と言っています。
経営の世界においては普通などくそくらえなのであり、「普通はそんなことはしない」というのは、経営者にとっては誉め言葉となります。普通のことをやるのにあなたの出番は必要ありません。
御社では「普通はやらない」ことをやれていますか? その事業はわざわざ御社がやる意味があることですか?
自社ならではのユニークな事業づくりを当社はこれからも応援していきます!
