【経営革新コラム】 儲かるキラーサービスをつくる社長の視点 第204話:御社の商品が売れない理由の理解
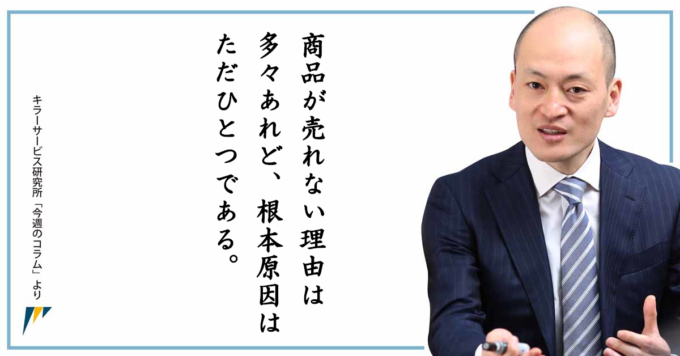
「商品が売れない理由って結局ひとつなんですけど、なんだと思いますか?」── クライアント先のN社長に私が問いかけました。
「え? ひとつっていうとやっぱりその商品に特徴がないってことですか? あ、でも価格とかもありますね…、ほかにも…」
N社長の口からはたくさんの「売れない理由」が出てきます。
「そうですね、そのどれもがあり得ますが、共通する理由はひとつなんです」
そう私がお伝えすると、N社長はじれったそうに続きを待たれました。
本当にちょっとしたことで全然売れなかった商品やサービスが売れ出すことがあります。それは価格設定だったり、キャッチコピーだったり、店舗のPOPだったり、パンフレットや広告の見直しだったり…。
しかしながら、なにをするにせよ絶対に欠かせない、ものを売るために必要なことがあります。それが「顧客のことを理解する」ということです。
「え? そんなこと?」と拍子抜けされた方も多いかもしれませんが、でも顧客(見込み客)のことをちゃんと理解していたら、ものは売れると思いませんか?
でも実際その商品が売れていないということは、やはり見込み客が考えていることと、売り手が考えていることがずれているということです。
そう言うと、「いや、ちゃんと顧客のニーズにあった商品になっているから、知ってもらえさえすれば売れるんです」と言ってくる人がいます。しかし、もし本当に見込み客のニーズをちゃんと理解しているのであればちゃんと広告が機能するはずです。
広告を出しても反応がいまいちということは、打ち出しているメッセージか、あるいは広告を出している媒体(メディア)が見込み客の思っていることとずれているということになります。
広告だけでなく実際のセールスでも同じことで、顧客を無視して一方的に商品説明をするセールスマンによく出くわしますが、顧客のことをちゃんと理解して、彼らの心に刺さるセールスストーリーを用意していれば、商品の説明などしなくてもその商品はちゃんと売れるはずです。詳しくは割愛しますが、当社では「セールスに商品説明は不要」と常々クライアント先にお伝えしています。
「商品を売るには顧客のことを理解しなければならない」── こう書くとものすごく当たり前のように見えて、実際にはこれができていなケースが非常に多いわけですが、なぜ顧客のことを理解することが難しいのでしょうか。
その理由として非常に多く見られることがあります。それは、「いい商品は売れる」との思い込みです。
もしいい商品であれば売れるのであれば、私の自宅や事務所には大量のモノで埋め尽くされているはずです。でも実際はもちろんそんなことはありません。なぜならお金も、場所も、そして買ったものを使うこちらの時間も限られているからです。皆さんにも「いいものだけど買ってない」ものはたくさんあるはずです。
同様に、御社の商品が思うように売れていないとしたら、見込み客には「買わない理由」があるということです。そしてそれは必ずしも「商品がよくないから」ではないのです。商品の良し悪し以外にも見込み客がそれを買わない理由は山ほどあります。
本当に優秀な営業マンは、売れたときよりも売れなかったときのことを重視します。そして、ときには買ってくれなかった顧客に丁寧にヒアリングしたりもして、買ってもらえなかった理由をしっかり把握し、それをセールスや次の商品企画に生かしていきます。
これは営業マンだけではありません。優秀な経営者は定期的に現場に向かいます。たとえばオイシックスの創業者である高島氏は創業以来毎月一般家庭の顧客を訪問しているそうですが、特に「(定期購入を)やめそうな顧客」の訪問を重視しているとのことです。これも顧客の「買わない理由」を自ら感じ取ろうとしているわけです。
「いいものであっても売れない」── ここを出発点にすれば、商品企画や販売戦略についての考え方も変わるはずです。まずは見込み客の「買わない理由」について目を背けずに、客観的な視点でしっかり向き合ってみましょう。それさえ事前に潰すことができれば、あとは「買う」という選択しかなくなります。
