【経営革新コラム】 儲かるキラーサービスをつくる社長の視点 第218話:社員を行動させるために社長が語るべきこと
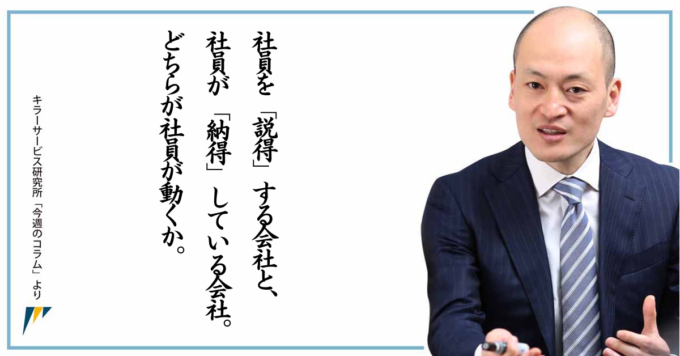
「『抽象度を上げて話す』というのはそういうことですかー。なるほど、理解しました」── 先日コンサルティングセッション終了後に酒席をご一緒していた社長の言葉です。
私がセミナーやコンサルティング中によく口にする「抽象度を上げる」ということについて、あらためて理解を深めたいとご質問されました。
確かに「抽象度」という言葉自体は普段あまり使わないかもしれませんが、我々は考えたり話たりするときに、普段から無意識にこの「抽象度の上げ下げ」を繰り返しています。
「抽象度を上げ下げする」というのは別の言い方をすると「抽象と具体を行き来する」ということになりますが、(具体的にではなく)抽象的に話しをすればそれが「抽象度が上がっている」ことになるのかというと、ちょっと違います。
抽象度を上げるというのは、「物事をより本質的に捉える」ということです。つまり「より高い視点で考える(話す)」ということになります。
少し例を上げてご説明すると、「私が飼っているチワワ」というのはかなり「具体」の話です。つまり抽象度は低い。これを一段抽象度を上げると、「チワワ(全般)」となり、さらに上げると「犬」、そのまた上は「動物」、「生き物」となっていきます。抽象度を上げて考えるというのは、私の飼っているチワワのことばかり考えるのではなく、犬について、あるいは生き物について考えるということです。
この「抽象度を上げて考える」ということを、経営者やビジネスリーダーは常に意識する必要があります。
「いや、犬についてなんて考えないけどなあ」ということではありません(笑)。ビジネスにおいて「抽象度を上げて考える」ことができないと、事業で同じ失敗を繰り返したり、社員が動いてくれなかったり、あるいは顧客の心が動かせなかったり…ということになってしまうのです。
抽象度を上げて考えないと同じ失敗を繰り返す。これはどういうことかというと、なにかで失敗したという事実(具体)だけにフォーカスして、肝心な「なぜ失敗したか」という本質(抽象)に目を向けないということです。よくいう「失敗から学んでいない」という状態ですね。クレームを起こしたらただ顧客に謝るだけ、という対応もこれに当たります。
これはなにかで成功したときも同じことが言えます。成功したという事実(具体)に酔いしれ、「なぜ成功できたのか」という要因をしっかり分析していなければ、その成功は次に活かせません。
たとえば大きな特注案件を獲得したとしても、その案件の重要な要素(なぜ顧客に刺さったか)を抽出して他の顧客に横展開できなければ、その受注は単なる一発案件で終わってしまいます。これは非常にもったいないことです。
つまり、何かの事象(具体)だけを見るのではなく、その裏にある「なぜ」を突き詰めることが大事なのです。
そしてこの「なぜ」を語ることができないと社員や顧客も動いてくれません、という話をしたいと思います。
おそらく経営者やビジネスリーダーである皆さんは、社員に対して「何をやるか(WHAT)」とか、「どうやるか(HOW)」といった指示は普段からされていると思います。
しかし、こういったWHATやHOWを伝えるだけでは、人はなかなか動いてくれません。これは心理学ではなく生物学で説明できることなんです。
ちょっと小難しい話になってしまいますが、これはヒトの脳の働きに関係しています。上記のWHATやHOWについての指示は「理屈(論理)」です。これは脳の大脳新皮質という部分で理解されます。これは脳の外側(表面)の部分で、まんじゅうでいうと皮の部分になります。
そしてなんと、この大脳新皮質という部分は、合理的な思考や言語を司るのですが、ヒトの行動にはつながらない(行動を司令しない)のです。
これが、いくら「何をやるべきか」を伝えても社員が動かない理由なのです。もちろん雇い主や上司の指示には基本的には従うでしょうが、そもそもの動機づけが弱いため、途中でやらなくなったり中途半端になったりしてしまいます。
では、社員が自発的に動いてくれるために何を伝えたらいいのかというと、それが「なぜ(HOW)」なのです。つまり、仕事上の個々の具体的な指示の前に、そもそも「なぜ」我々はこの事業をやる必要があるのか、自分たちがこの事業をやる目的、あるいは自分たちの存在意義といったことを、彼らと共有することが非常に大事ということです。
この「なぜ(WHY)」を伝えると人は動いてくれるのか、これも脳の仕組みから来ています。
「なぜそれをやるのか」というのは往々にして理屈ではありません。経営者として「それをやりたいから」とか「それをやるべきと思うから」という「個人的な感情」から来ているはずです。
そういった「感情」に対しては、相手も「感情」で受け止めます。そしてそれは脳の大脳辺縁系という部分が司ります。脳の内側、まんじゅうでいうとあんこの部分です。
この大脳辺縁系という部分は、感情、信頼、忠誠心などを司ると言われています。そして、ヒトの行動のすべてを司り、すべての意思決定をするのですが、なんと言語能力はないらしいのです。
つまり、いくら言葉で説明を尽くしたとしても、それが相手の感情を揺さぶるようなものでなければ、行動を司る大脳辺縁系が反応してくれないということです。
ですから、WHATやHOWといった具体的な指示だけ出していても駄目ということなんです。もっと経営者の想いである「そもそも論」を伝え、それに共感してもらう必要があるのです。
これは顧客に対しても同様です。自社の商品の特徴や使い方、製法といったことの説明(WHATやHOW)をいくら伝えたところで、相手の感情は動きません。自分たちのそもそもの想いや価値観を相手にぶつける必要があるのです。
わたしたちはついビジネス脳を使って相手を「理解」させようとします。しかし相手はそれで理解はしても納得はしません。ヒトは感情で動く生き物なのです。
当社が「競合他社がやっていない特別対応」の構築にこだわっているのもこの点にあります。どこにでもある商品やサービスを提供するのでは、顧客も自社の社員も心が動かないのです。顧客も説得はされても納得はしないのです。
自社の社員の心が弾むような商品やサービスを提供するならば、もはや小手先の説得テクニックは不要になります。相手の大脳辺縁系が反応して行動してくれます。
皆さんの社員や顧客は、説得ではなく、納得や共感、あるいは信頼で動いていますか?
