【経営革新コラム】 儲かるキラーサービスをつくる社長の視点 第235話:経営者が習慣にすべき、業績が上がる「ある習慣」
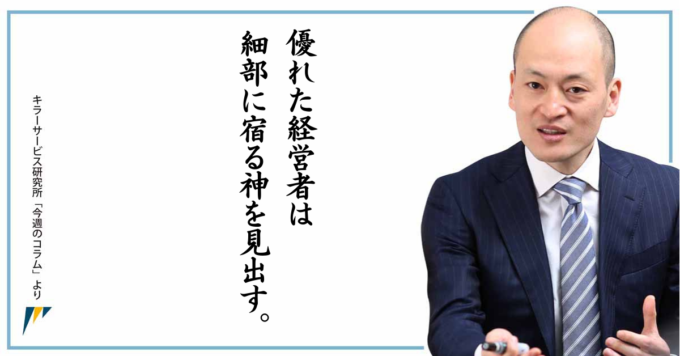
「風呂にお湯を溜めているつもりが、栓が抜けていたって訳ですか…」──Y社長はなんとも言えない表情です。
打ち出している販売施策で反応が出ている割に全体の顧客数が伸びていないので、おかしいと思ってデータを出してもらったところ、既存顧客の離反が相当あったことが判明したのでした。
ここ数年、毎月の顧客数(実際に注文があったアクティブ顧客の社数)はしっかり確認してこられた同社ですが、顧客の中身がかなり入れ替わっていることには気づけていなかった状況です。
このケースのように、分析結果の深堀があまく、誤った現状認識をしてしまうことはよくあることです。
データ分析をする上で非常に大事な2つの考え方があります。まずひとつ目は「全体像をつかむ」ということです。
これは、売上や利益、出荷数や顧客数といった主要な数字を商品群別やエリア別などで見て、業績の全体的な傾向を把握するアプローチとなります。
言うなれば、簡易的な健康診断でサクッと自分のいまの健康状態を把握しようとすることに似ています。なにか大きな異常が出ていないか、大まかなトレンドをチェックするということです。
大まかなアプローチといっても、このレベルですらできていない企業は世の中にたくさんあるのではないでしょうか。私が関わらせていただいた企業においても、売上数字はさすがに把握しているものの、商品別の売上や顧客数となると確認していないというケースが多々ありました。
つまり、税理士が出してくる試算表はちゃんと見ているが、自分たちが持っているデータは活用できていない状態です。こういう状態にある会社は、要は戦況を無視しながら戦っているようなものですから、失礼ながらまったく戦略的な経営ができていないはずです。
そのように、データ分析のひとつ目のアプローチである「全体像をつかむ」ことすらやっていない会社は論外として、二つ目のアプローチができていなくて現状をつかみ損ねている会社は非常に多いと想像します。
その二つ目のアプローチが「個に迫る」というものです。
これは文字通り、データを深堀して個々の数字に迫っていく手法となります。
たとえば冒頭の例でいうと、ここ一定期間の間に獲得した新規顧客と、古くから取引のある従来顧客に分けて顧客数の推移を確認し、さらに離脱した顧客についてはちゃんとバイネームで社名を確認するような粒度です。
いうなれば健康診断から一歩踏み出して、人間ドックを受けるようなものでしょうか。
そして、「個に迫る」アプローチでは、単にデータ数字を確認するだけに留まりません。さらにその数字の裏側にある実態に迫っていきます。
上記の例では、顧客が離脱した理由をヒアリングなどで一社一社確認することがまず第一歩となります。
さらには、社員が実施したヒアリング内容に対して、経営者としてどうも納得がいかない点があると感じた場合、経営者自らが実際に顧客を訪問して実態を直接把握することも必要になります。
これは経営者の動物的な勘というやつです。「なんか臭うなあ」という直感が的中し、データだけ見ていたらわからなかったような、とんでもない実態が明るみになることも珍しいことではありません。殺人事件を捜査する刑事の「現場百遍」ではないですが、現場にこそ事業発展の鍵が転がっていたりするものです。
実はこの「個に迫る」という考え方は、私がミスミ勤務時代に当時の三枝社長に叩き込まれたものです。中途半端な事実の押さえで戦略的な判断を下した場合など、「もっと個に迫れ!」と叱られたものです。ちゃんと事業の現場(=戦場)で何が起こっているのかを皮膚感覚で把握しろというわけです。
現に三枝氏自身も「なにかがおかしい」と思ったらすぐに現場に駆けつける人でした。時には海外の物流倉庫に現地駐在員に内緒で飛んで行ったこともあるぐらいです。
この「個に迫る」アプローチを自社において習慣づける必要があります。そのための手法はシンプルです。それは、社長が常に社員に対して具体的な質問をすることで実現します。
例えば、これから新規顧客を攻めるというタイミングであれば、
「目標10社獲得!」と計画を立てるだけでなく、10社獲るためにはターゲット顧客は何社を抽出するのか? その時の考え方はどのようなものか? そしてそれらは何という会社なのかを確認する。
実際の電話や営業訪問が始まったタイミングでは、「新規営業は順調か?」とバクっとした質問をするのではなく、「実際にどの会社に行って、どのような商談になったか」を先方のセリフレベルで把握する。
そして新規顧客を獲得できた際には、単にねぎらうだけではなく、当社から買ってくれた理由や、どこから切り替えたかなどをできるだけ確認する。
このように、とにかく具体的に社員に対して質問を続けるのです。これは担当社員を信用するとかしないとかいうレベルの話ではありません。彼らと具体的な事実を押さえた会話をすることで、意味のないふわっとしたやりとりがなくなり、確実に事業が前に進むようになります。
さらに、そのような質問の応酬は社員にとって格好の訓練となります。事実の深堀は思考訓練になりますし、また具体的な行動を起こしていく習慣づくりにもなっていくはずです。
御社では社長が社員と個に迫った議論を持てていますか?
抽象的でふわっとしたやり取りではなく、具体的で行動につながる会話ができていますか?
