【経営革新コラム】 儲かるキラーサービスをつくる社長の視点 第248話:経営者が知っておくべき「事業の軸」をつくる方法
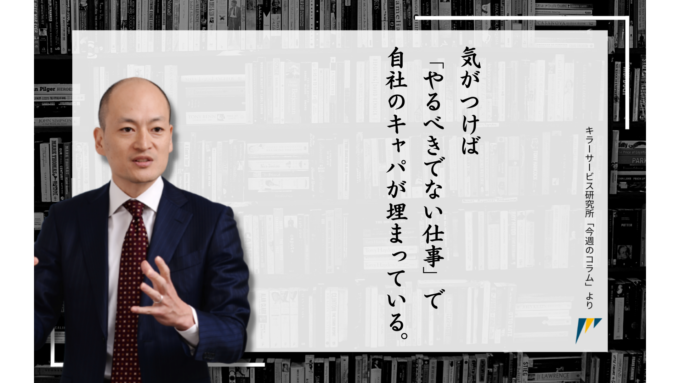
先日、「すごい工場」という本を出されている愛知のスチールテックさんを見学に行ってきました。
同社は新工場への全面移転を機に「環境整備」という取り組みを実施し、ピカピカで合理的・効率的な職場環境をつくりあげました。
その取り組みの第一歩が「5S」でいうところの「整理」、つまり要らないものを捨てるという基本的なことから始められたわけですが、基本的といってもこの「整理」が非常に大変だったとのこと。
なぜ大変かというと、「要らないものを捨てろ!」と社員に言ったところで、彼らは「要らないものなんてない」と思っているからなんですね。
デスクの引き出しや共用のキャビネットに置いてある書類、PCに保存しているファイル、製造現場にある材料の端材、工具類、もう錆び付いている古い在庫…これらも「いつか必要」と考えるとどれも捨てられない。
しかし、こういったものは捨ててみてはじめて、そこにあるだけで不要なコストだったということがわかります。作業効率が上がることは当然ですが、なにより視界がすっきりして、それはそのまま思考をクリアにすることにもつながります。
以上のような職場環境の整理については、特に製造業であれば私があれこれ言わずともその重要性についてはよく理解されていることと思います。
ところが、事業にとって「無駄」なものは、なにも書類や不良在庫といった不用品だけではありません。もっと無駄であり、真っ先に排除したいものがあります。
それが、「儲からない受注案件」です。
手間ばかりかかって利益が取れないもの、難易度が自社の能力を超えていてロスやクレームが頻発するもの、あるいは単なる作業でどこでもできるもの…。
そういった「利益の取れない案件」で社内のキャパの一定量を埋めてしまうことこそ、非常にもったいない「無駄」であると言えます。
そう言うと、「そんなこと言ったって、そんなに儲かる案件ばっかりじゃないんだから」とか、「キャパが空いている以上そういうものも取っていかないと…」とおっしゃる方も多いのではないでしょうか。
しかしながらこれが要注意なのです。ものごとは放っておけば乱雑に増えていくというエントロピーの法則が働きます。最初は「設備も空いているし、ちょっとだけならいいか」と思っていても、気がつけば現場は儲からない案件で一杯になり、よくある「忙しいのに儲からない」という状態ができあがります。
この状態から抜け出せない経営者の特徴としてよくあるのが、「お客様のためにやらないとしょうがない」と思い込んでいることです。
「お客様のために」と言って儲からない案件を受けて社員にせっせとやらせる。これでは社員は報われません。本当にお客様の役に立つ仕事をしているのならば、しっかり利益が取れる値段で受けることです。それを顧客が拒否するのならそれまでの関係です。
自社の良いところを認めてもらって、しっかり利益の取れる単価で受けていただく。これを徹底することで会社経営は非常にシンプルになります。エントロピー増大を逃れることができます。そして、事業に軸ができてきます。
事業の軸を見つけるためには、「なにをやらないか」を決めることです。これが社内外への強いメッセージになります。やらないことを明確にすれば自社の強みが浮き上がります。顧客にもそれで覚えてもらえます。
「別にうちがやらなくてもいい仕事」で溢れている会社は、本当にやるべき仕事に絞ることは勇気がいることでしょう。ここで腹を括れるかが勝負どころとなります。思い切って自社の軸を打ち出していけば、必ず将来に自らの決定に救われる時がきます。現に当社のクライアント先の経営者でも、「あの時に思い切って儲からない仕事を切ってよかった」と回想される方が少なくありません。
仕事を切れば、当然その穴を埋めようと全社で動くことになります。その時に歯を食いしばって「自社が本当にやるべき仕事」を取ってくれば、経営は変わります。事業構造を進化させることができます。
もし御社が、「儲からない作業的な仕事をせっせとこなしている」という状態にあるとしたら、その延長線上に「納得のいく姿」があるかどうかあらためて考えてみてください。「いや、ない」ということならば、いまから変えるしかありません。将来の自分に納得のいく未来をプレゼントすることができるのは、いまの自分だけです。
顧客にとって「特別な存在」になるべく、いまから変化を起こしていきましょう。
