【経営革新コラム】 儲かるキラーサービスをつくる社長の視点 第249話:幹部を研修に出しても成果が出ない理由
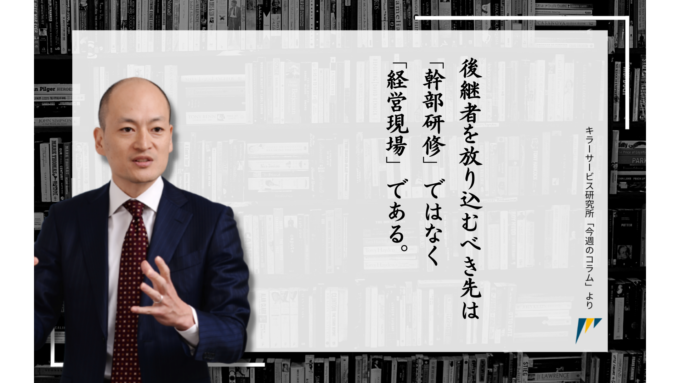
「一年間幹部を研修に行かせたんですが、実際の成果には結びつかなくて…」── 先日オンラインにて個別相談を受けていただいた経営者の方がこう漏らされました。
この方に限らず、当社が関わらせていただいた会社の経営者の中にも、社員に高い研修を受けさせたがあまり意味がなかったとの感想を口にされた方が少なからずいらっしゃいます。
それもそのはず。何事も「なんのためにやるか」との思考を当人が持っていないとしたら、せっかく学んでも身につかないということは容易に想像できます。
とはいえ社員を研修に送り出している社長からすれば、「なんのためにって、そりゃあ当然彼らに経営幹部として育ってもらうためだろう」と思われていることでしょうし、実際研修を受けている当人も「この機会を利用して経営をしっかり学ぼう!」と前向きな気持ちで参加されている方も少なくないと思います。
それでも経営についての研修が無意味に終わってしまうことが多いのはなぜなのか? それは大きく2つの理由が考えられます。
まずひとつには、やはり「当の本人が学ぶ必要性を感じていない」という場合がほとんどでしょう。前述のような「経営を学びたい」という漠然とした願望は必要性とはなりません。これは「英会話を習いたい」と言ってる人間の9割以上が永遠に英語をマスターできないのと同じことです。どうしてもそれをマスターしないといけない理由が希薄なのです。
「学ぶ必要性」あるいは「成長する必要性」を持つために絶対的に必要なものがあります。それは「痛み」です。「このままではマズイ」と当人が痛みを持つような経験が必要なのです。
前述の「英語をマスターしたい」という場合であれば、英語がうまく話せなくて職場で悔しい思いをしたとか、何かの機会を逃したとか、そういった「心に刻まれる痛み」がなければ、「なにがなんでも英語をマスターしよう」というところまで気持ちがいきません。
経営に関しても当然同じことです。経営幹部とは名ばかりで、普段は経営ではなく「販売」や「製造」や「購買」といった業務に従事している社員にとって、「経営者になるためにもっと成長しなければ!」と思わされるような痛みを感じることはまずないのではないでしょうか。
将来自社の経営を担ってもらいたい社員に、そのような「痛み」を感じさせるために必要なことはただ一つです。それは、当人を「経営の場」に放り込むことです。具体的にいうと経営戦略を立案し、その実行指揮を執らせるということです。
「経営戦略の立案と実行」── このように言葉で書けば非常に簡単な表現であっても、実際にやるとなったらこれは大変なことです。初めからスイスイうまくいくはずがありません。
従来の自分の担当部署のことだけではなく、会社や事業全体のことを考えて実行するとなると、単なる知識だけではなく、思考力、リーダーシップ、コミュニケーション力、勇気、胆力…さまざまな点において「一段上」にいかないといけないことがわかるはずです。
そうしてはじめて本当の意味で「経営を学ぶ必要性」を感じることができるようになります。
では、その段階になったら研修に行かせればいいのかというと、そうはいきません。これは、研修に行かせても成果が出ない2つめの理由となりますが、「経営の一般論を聞かせても意味がない」からです。
ビジネスにおいて必要となる「答え」はその時の状況によってまったく異なります。もちろん、事業戦略の構築と実行における「原理原則」となる考え方はありますが、その応用の仕方は100社あれば100通りとなり、何一つ同じものがありません。
つまり、経営を教える側もその状況の中にいる必要があるということです。新規事業の立ち上げや不振事業の再建などはいい例で、それを指導する人間もそのプロジェクトに入り込まなければ、もっというとそのプロジェクトを設計する立場にならなければ、それを成功に導くことなど絶対に無理です。
当社が一社一社の「個別指導」にこだわる点もこれが理由です。グループコンサルのような形式で座学を指導するのではなく、その企業の事業環境、組織の状態、経営者の想いや社員のマインドなど、さまざまな要素を踏まえてその企業にあった「個別解」を提示しています。泥臭い事業変革となりますが、その過程で経営者や幹部が本気になっていかれます。
よくある幹部研修の案内ページには「異業種の経営者と横のつながりができる!」とアピールされていたりしますが、そういうものなのです。知人が増えたり、いくつか知らなかった理論や言葉を覚えたり、(いっときは)やる気が出たりと、メリットはないではないでしょうが、事業革新とは別の話になります。
もし、本気で育てたい! 後継者にしたい! と思う人物がいらっしゃるのであれば、事業変革のプロジェクトを任せてみること、これに尽きます。その過程で社長がビシバシしばいて育てるのです。事業を創ることができる経営者に育てたければ、それをやらせてみることが一番ということです。
御社では後継者や幹部候補を「経営」に関わらせていますか? 単なる担当者として日常業務に埋もれさせていませんか?
