【経営革新コラム】 儲かるキラーサービスをつくる社長の視点 第252話:どうしても新規事業が立ち上がらない企業へ
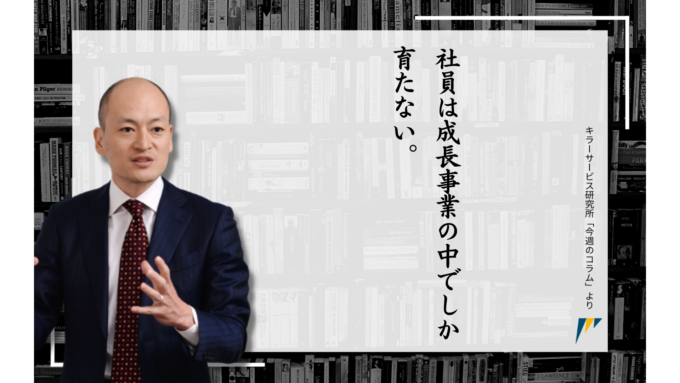
機械商社のM社は、個々の社員がバラバラに動く営業から、チームで戦略を練って動く「組織力営業」への移行に挑戦しています。
「新規をやる時間はなかなか取れないですねえ…」ー そう発言する営業マンに対して、営業部長がすかさず基本的な考え方を伝えます。
「みんな既存顧客ばかりに行って、残った時間で新規をやろうとするけど、それでは新規なんて永久にできない。」
「発想を逆にして、アポは1ヵ月分の新規のアポを全部取ってから、残った時間で既存に行くというぐらいにしないと!」
まさにこの営業部長の言うとおりです。新規顧客の獲得は、意図して優先的に動いていかないと取れるものではありません。
同社ではこれまでこの営業部長が別格の成績を叩き出していたため、他の営業マンは「部長は別格」「部長にしかできない」といった意識を持っていましたが、今後は「部長のやり方が当たり前」となるように、営業部としてさまざまな方針を定め、営業活動の標準化に取り組んでいる最中です。
この会社のようにまさしく「営業のプロ」と呼べるような一流の人材がいる会社であっても、そのやり方を他の営業マンに浸透させることは、なかなか難しいものです。
ましてや自社の営業マンがだれもそこまでのレベルにない会社の場合、外部人材を活用するなどして強制的に「仕組み化」を進めないと、いつまで経っても「売れる組織」にはならないでしょう。ただ社員に言葉で発破をかけたり、ノルマを課したりしても、組織としてレベルが上がるということは絶対にありません。
ところで、先ほどの「新規が先、既存は後」という考え方。これはあくまで営業のアポ取りの話ですが、これとまったく同じことが、その会社の「新規事業」に関しても言うことができます。
つまり、新規事業が立ち上がらない会社というのは、間違いなく「既存事業を優先」しているということです。
「いや、新規事業ばかりに注力して既存事業をおろそかにしたら、事業がめちゃくちゃになってしまうよ」と思われる経営者も多いことでしょう。
しかしながら、継続的に成長する企業というのは、既存事業の忙しさにかかわらず、必ず常に新規事業に一定の時間と労力を割いています。「いつか落ち着いたら…」と新規事業を先送りしたりしません。前述の「新規を取れない営業マン」のような考え方はしないということです。
新しい事業というのは、立ち上がってから軌道に乗るまで、当然ながら時間がかかります。既存が忙しかろうと暇だろうと、「常に」取り組まないと絶対にものにならないのです。
事業にはライフサイクルがあります。導入期、成長期、成熟期、衰退期と分けることができます。この4つのステージを以下のように分類してみましょう。
導入期=新規事業
成長期=新規事業
成熟期=既存事業
衰退期=既存事業
いかがでしょうか。もしこのように分類するとすると、「既存事業に注力」というのがいかに危険で偏ったことであるかが理解できると思います。成熟期にある事業ばかりやっていると、その先には「衰退」しかないということです。
「常に新規事業に取り組む」というのは、つまり「事業を導入し、成長させ、それが成熟期に入ったら、すぐさま新しい事業を導入する」ということになります。これが成長を続ける企業がやっていることです。営業と同じで、やはり「常に新規」が大事なのです。
人はつい目の前のことに注力しがちです。経営者が常に足元の受注の話しかしないとすれば、当然ながら社員の意識もそこに集中します。
ここで大事になるのが「仕組み化」の発想です。つまり、強制的に「新規事業について考える仕組み」を導入することが必要になってきます。
具体的には定期的に新規について議論する「場」を持つことです。つまり定例会議を持つことで、いやでも「目の前のこと以外のこと」について話を進めることができるようになるのです。
この「場」を持たない限り、社員がやることは「成熟期にある事業の衰退を先延ばしする」行為に終始することになります。活気も、喜びも、(いい意味での)驚きもない。そんな組織になってしまいます。
「社員は成長事業の中でしか育たない」
私がかつてお世話になったミスミの三枝社長(当時)がよく言われていた言葉です。
事業が衰退期にある会社では、社員の意識が「内向き」になりがちです。そうなると「政治的」「官僚的」になり、発想も動きも硬直化します。
とにかく成長事業を持つこと。それで会社経営の多くの問題が解決します。これは当社がこれまでさまざまな企業の事業革新をお手伝いする中で実際に見られた現象です。事業の成長が社員の成長につながるのです。
社長以下、社員一丸となって事業を成長させる。これは何事にも代え難い喜びとなります。この喜びがある会社とない会社、どちらを選ぶか、答えは明確です。
経営者が仕組みで仕掛けていくことで、この喜びは生まれます。
