【経営革新コラム】 儲かるキラーサービスをつくる社長の視点 第254話:「組織は戦略に従う」のか「戦略は組織に従う」のか?
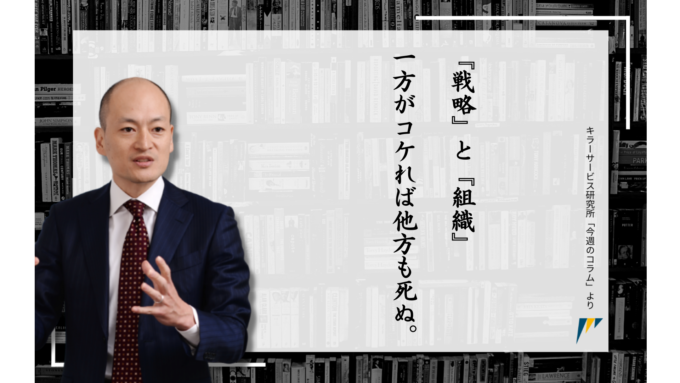
「もっと根本的にグループの経営戦略を見直して、それに沿って組織をつくっていきたいと思います」ー ここ数年関わらせていただいているクライアント先の社長の言葉です。
複数ある事業それぞれの事業戦略の見直しとともに、グループ全体の事業承継も含めた重要な経営課題について、自分がしっかりしているうちに手を打っていきたいとのこと。
非常に賢明なご判断だと思います。というのも、仮に社長が突然亡くなっても会社が大丈夫なように戦略と仕組みを整えておくことは、いかなる会社も取り組むべき必須のことだからです。これは社長の年齢に関係なくです。(50代で突然死なんてこともいまどき何も珍しくありません)
「戦略をつくり、それに合った組織をつくる」ー これは経営学者アルフレッド・チャンドラーが言うところの「組織は戦略に従う」という考え方です。
これは、極端にいうと『戦略>組織』ということになりますが、組織を「戦略を実行するための手段」ととらえた場合、これは当然の考え方となります。
組織活性化のために、研修講師を自社に招いて社員研修なんかを行う企業がよくありますが、どんな戦略を立てて、どんな強みを構築しようとしているかで、組織をどういじるかは当然変わってきます。
エクセレントカンパニーを分析してみたら社員が非常に元気で明るいということがわかったとして、じゃあ社員が明るくなるようなコミュニケーションのやり方を導入したら会社がエクセレントカンパニーになるのかというと、当然そんなわけはありません。
一方で、「戦略は組織に従う」という考え方もあります。これもまた真実で、どんな戦略を描いても実行できなければ絵に描いた餅になりますから、組織の実力値は戦略立案の段階から非常に重要なファクターとして考慮されるべき点となります。
「いやいや、組織の実力が足りないんだったら、社員を総入れ替えしたっていいんだよ。あくまで戦略重視だ!」という強気の考え方もあるとは思いますが、それにしたって結局できる人を連れてこないといけないのですから、やはり広い意味では「戦略は組織に従う」ということになります。
しかも、このような人員の総入れ替え、組織のスクラップ&ビルド的なやり方は、欧米ではともかく日本では実際問題としてなかなか難しいということもあります。
日本は基本精神として「和をもって尊しとなす」文化です。仲間の多くが退職させられた場合に、残った社員が意欲的に働いてくれるかというと、どうでしょうか。しかも、この人材不足の日本でそんなに多くの優良人材を雇うことも不可能です。ことさら日本では戦略立案にあたって組織の実力値を考慮する必要があるということです。
つまり、組織は戦略を実行するための手段であるから、戦略なくしては目指す組織の形も見えてこないが、一方で戦略は現状の組織の実力値の制約を受けるため、組織力を見極めることなくして戦略は描けないという、「戦略と組織の相互依存」という関係があるわけです。
何が言いたいかというと、企業経営を進める上で「戦略」と「組織」は自動車でいうとハンドルとタイヤのようなもので、どちらが欠けても前に進めないということです。
戦略はいわば「山を登り切るためのルート(道筋)」です。これを示すことなく社員のケツを叩いたところで頂(ゴール)に辿り着くことはできません。
一方、継続して組織力を高めていかなければ、せっかくゴールに到達できる最短ルートが見えているのに、斜面が急すぎて「うちの社員では登れない」なんてことになってしまいます。
ではどのようにその両輪を進化させていけばいいのか。
その答えはシンプルで、トップがストレッチした戦略を描き、それを社員に実行させることです。
リーダーが、自社の組織(チーム)がどこまでのストレッチに耐えられるかを見極めながら、しつこくフォローして橋を渡り切るまで伴奏する。その現場経験を踏ませるしか方法はありません。
リーダーが戦略を描き、それをチームに落とし込もうとしても、それに呼応し燃えて動くような「火ダネ」となる社員は全体の1割いたらいいほうでしょう。残りの大半はシラケ社員です。
それでも、リーダーは火ダネ社員に心に火をつけ、燃え上がらせ、その炎が飛び火してシラケ社員をも燃え上がらせるまでやるしかありません。ときにはリーダーがストレッチの限界を見誤り、燃え上がるどころか焼き殺されそうになる社員も出てくるでしょうが、そうしながらリーダーもメンバーも成長していくしかないのです。
そのためにはまず「何に燃えるか」を決めなければなりません。やはり戦略ありきなのです。
戦略なき会社にあるもの、それは「惰性」です。
