【経営革新コラム】 儲かるキラーサービスをつくる社長の視点 第259話:業績好調な会社ほど「切迫感」が必要である理由
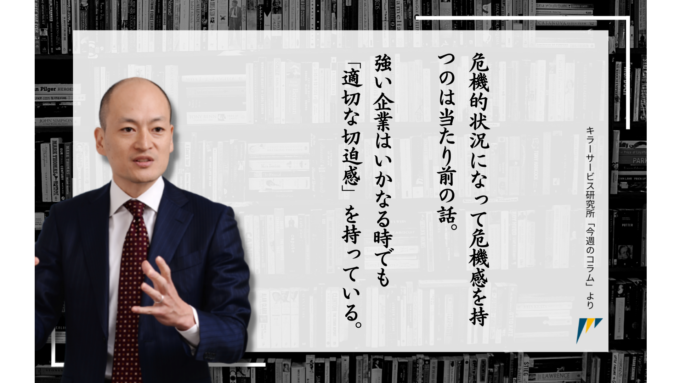
「実はうちはコロナで追い風が吹きまして、業績がよかったものですから、今のうちに次の手を打ちたいと思いまして…」── 拙著を読んでずっと気になっていたという社長が先日スポットコンサルにお越しになりました。
コロナもあって業績が落ち込んだために、「こりゃなんとかしないと」とご相談にこられた方は複数いらっしゃいましたが、「コロナで儲かったから来た」とおっしゃるケースははじめてです。
前者の「業績が落ち込んだだめに事業改革に着手するケース」と、後者の「業績が良かったために事業改革に着手するケース」、それぞれ一長一短があります。
業績の落ち込みをきっかけに事業改革に着手することのメリットは、なんといっても「追い込まれていること」にあります。つまり、組織に切迫感がありますから腹を括りやすいということです。
いまやっている事業を変革することに多くの社員は抵抗を覚えます。それは何も「ダメな社員」がそうなるわけではなく、誰にでも見られる現象です。
現場の業務を担っている社員にとって、「自分が毎日やっていること=自分そのもの」というぐらい業務にアイデンティティを感じるものです。また新しいことをやるとなると現場の混乱も容易に想像できますから、事業変革などやりたいとは思わないのが普通です。
よく「痛みを伴う改革」という言葉が使われますが、現状維持が一番楽ですから「改革=痛み」なのであり、「痛みを伴わない改革」などないと言えます。
ですから、事業変革を起こすには、社員にそのような「痛み」に向き合わせるための原動力が必要になってきますが、大幅赤字など業績の落ち込みがその原動力となり得るわけですね。
もっとも、業績の落ち込みが個々の社員にとっての痛みとなるためには、その業績悪化がコロナのせいでもロシアのせいでもなく、自分たちの責任だと認識させるためのロジックが必要になりますし、業績と報酬がリンクする仕組みも必要とはなりますが、「ここで奮起しないと後が無い!」と思わせることができれば、それは事業変革の大きな原動力になります。
一方で、業績が良かったために事業改革に着手するケースのメリットは、なんといっても「時間軸に余裕があること」です。
足元の業績に余裕がないと、改革のゴールが「来期の黒字化!」といったことになりがちです。結果、抜本的な戦略の見直しではなく、営業やマーケティングの強化、ターゲット顧客の見直し、オペレーションの効率化といった「戦術」レベルの話に終始するケースがほとんどでしょう。
業績が好調なうちに次の一手を打てるのであれば、その一手の選択肢は大いに広がります。脱下請けのための自社商品の開発、B to BからB to C領域への進出、EC事業の立ち上げ、ものづくり企業から総合サービス業への転換などなど、事業を抜本的に変革する道を選ぶことができます。
こういった「時間軸が長くとれることのメリット」は経営者であれば容易に想像がつくことだと思いますが、問題はそのデメリットの方で、これを乗り越えることが難しいのです。
そのデメリットとは「社員が事業変革の必要性を感じない」ということです。
足元の受注が好調で現場も大変に忙しい…そんな状況で社員に対して「事業を変革しよう」とか、「新規事業を立ち上げよう」と言ってもやはり響かないでしょう。「それどころじゃない」と反対されるケースが多いのではないでしょうか。
いくら経営者が事業変革の戦略を描いても、実行部隊である社員たちが自分ごととして動いてくれなければ何にもなりません。せっかく時間軸に余裕があっても変革シナリオは不発で終わってしまうことでしょう。
では、業績が好調なうちに余裕を持った事業変革プランを描き、それを社員たちに積極的に取り組んでもらうためにはどうすればいいのか?
それは「成り行きのシナリオ」を正しく見せることです。
「成り行きのシナリオ」とは、このまま大きな手を打たずに現状維持でやり続けた場合の流れと顛末を明らかにしたものです。
商売には必ずライフルサイクルがありますから、時間の経過とともにやがて陳腐化して儲からなくなります。これは人が例外なく時の経過とともに「死に向かっている」ことと同じことです。事業も放っておけば必ず死ぬのです。
しかしながら、社員(特に経験の少ない若い人)にとっては「事業が死に向かっている」ということを実感しにくいものです。ニュースで大企業の倒産事例は知っていても、まさか自分の会社が傾くなんて夢にも思っていない人がほとんどなはずです。
だからこそ、自分たちの事業が「成り行きだと何年ぐらいでどうなってしまうのか」を、ただの脅しではなく論理的に説明する必要があります。痛みを先取りするのです。
「危機感」や「切迫感」をリーダーが人為的に発生させることが必要です。本当にやばい状況まで待っていては絶対に駄目だということを社員たちに示し、そうならないように新たな挑戦に彼らを導く。それがリーダーの役目であり、強い企業が必ずやっていることなのです。
御社では適切な切迫感をリーダーが作り出せていますか? ゆっくり自然死的に衰退していませんか?
もし後者であれば、ここで成り行きのシナリオをしっかり直視し、事業変革へと舵を切っていきましょう。
