【経営革新コラム】 儲かるキラーサービスをつくる社長の視点 第263話:経営者が持つべき「社員を動かす心得」
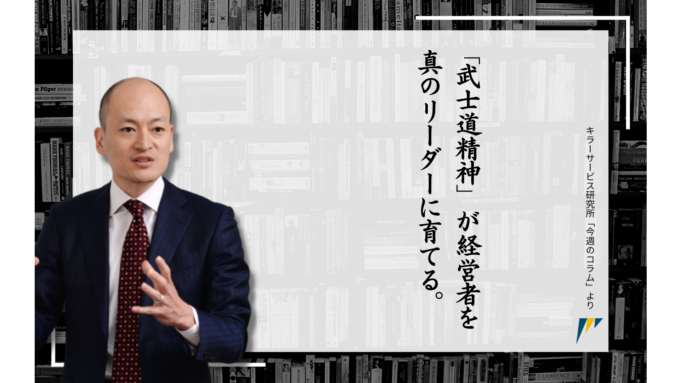
「先生はビジネス書はあまり読まれないとどこかで言われていましたが、じゃあどんな勉強をしてるんですか?」── 先日オンラインの個別相談を受けられた社長と最後に談笑をしていたときに出た質問です。
自分も経営に関する本を出しているぐらいですので、別にビジネス書を否定しているわけではないのですが、そういった本を読み漁っていた経営者がある時から孔子や老子といった中国古典を読んだり、仏教や神道を学んだりされるということはよくあることです。
「やり方よりあり方が大事」とよく言われているように、長くやっていると「ノウハウではなんともならない世界」の大事さを痛感させられ、経営者として(あるいは人として)一段レベルを上げるためにそういった抽象度の高い学びに触れたくなるということでしょう。
「あり方を磨く」というのはそれこそ非常に抽象的な表現ですが、別の言い方をすると、経営者としての矜持を持つこと、自分の美意識や世界観を高めること、人間の本質を知り自分を律することを覚えること、相手の立場に立てる器量を持つこと…といったことになるでしょうか。
これらを一言でいうと「教養を身につける」ということになると思います。世間では「教養がある」=「幅広い知識を持っている」といったニュアンスで言われることも多いですが、本来は上記のような内面(精神性)が高まった状態を指すものです。
ではそんな「教養」を身につけるために何を学んだらいいのか?というのが、冒頭の経営者同様多くの方が持つ疑問だと思いますが、実は戦国時代から江戸時代にかけて日本のリーダー(=武士)が教養を身につけるために例外なく取り組んでいたことがあります。
それが「剣術」です。
「教養」と「剣術」なんて一見なんの関係もないように聞こえるかとは思いますが、実は武士は剣術をやることによってリーダーとしての素養を身につけていたのでした。
そう言われてもピンとこない方がほとんどだと思いますが、これは実際に真剣を握ってみると誰しもそのニュアンスを体感することができるものです。
初めて剣を握ったときに驚くのがその重さです。「えっ、こんなに重いの?」と思います。これを一体どうやって振れるのかと思うぐらいです。そしてそれはただ重いだけではなく、簡単に人を殺せる切れ味を持つものですから、握るだけで緊張します。文字通り「これは真剣にやらないとヤバい…」とわかるわけです。
この重さは経営者の責任の重さそのものでしょう。人を切る力を持っているが、その使い方を間違えると仲間や自分をも傷つけることになりかねない。よほど鍛錬を積まないと剣を使いこなせないのと同様、経営者も真のリーダーになるためには努力と覚悟が必要となります。
剣の握り方も慣れないうちは難しいです。小指と薬指の二本指で軽く握るのが正しい握り方なのですが、最初はどうしても5本の指でぎゅっと力を入れて握ってしまいます。
二本の指で剣を握り、あとの三本指はゆるゆるにして余裕を持たせることで手の内に「遊び」が生まれます。この「遊び」を残しながら力を抜いて振ると剣の切先(きっさき)はビュンといい音を出して走ってくれます。
ところが、重い剣をコントロールしようと強く握ってしまうと、剣はまったく走ってくれません。ただ単に重い棒を振ったような感じになり、剣の持ち味がまったく生かされないのです。
これは社員を動かす心得にも通ずるものです。手綱を締めすぎると彼らはガチガチになって動いてくれません。社員を動かすためには「遊び」を持たせることです。三本の指は遊びを持たせて思い切って彼らに任せる。そして残り二本の指で責任者としての責任はしっかり果たす。そうすることで、彼らは安心して持ち味を発揮してくれます。
また、剣は速く振ればいいというものではありません。剣は打撃ではなく斬撃(ざんげき)ですので、刃先の軌道を真っ直ぐにしないとうまく斬れません。これを「刃筋を通す」といいますが、まさにこれも経営者の心得に共通します。筋の通らぬリーダーについてくる者はいません。社員に動いてもらうためには、ただ力任せに指示を出すのではなくきちんと説明し筋を通すことです。
また、戦国武将が好んで使った大ぶりの剣を「太刀(たち)」と言いますが、これは「断つ」という言葉から来ていると言われています。
甘え、怠心、慢心、誘惑、悪い流れ…そういったものを自ら断ち切る心掛けを常に持つために、常時携帯する刀を太刀と呼んだとか。
これは名だたる経営者が時に経営者に必要な素養として「切断力」を挙げることと一致します。経営が悪くなる要因の多くは、悪習を断ち切らず「ずるずると」やってしまうことにあります。惰性にまかせてきた「経営の流れ」を切断し、組織の新しい方向を導き出し実行する。それができるのは経営者だけです。つまり経営者は必要なときに躊躇なく太刀を振るう必要があるということです。
以上、剣をやることが経営者としての素養を高めることにつながる理由についてお伝えしました。ここでのポイントは「なので剣をやりましょう」ということではなく、リーダーとしての心構えは武士も経営者も同じだということです。
「剣心一如」という言葉があるとおり、剣は心によって動くものであり、剣と心は一元的なものです。剣を振り回しても振り回されても剣は仕事をしてくれません。
人もまったく同じです。相手を理解し、相手と一如の境地に至ることで彼らは志を共にしてくれます。
ここが経営の醍醐味と私は思います。
