【経営革新コラム】 儲かるキラーサービスをつくる社長の視点 第266話:KPIマネジメントを正しく機能させる考え方
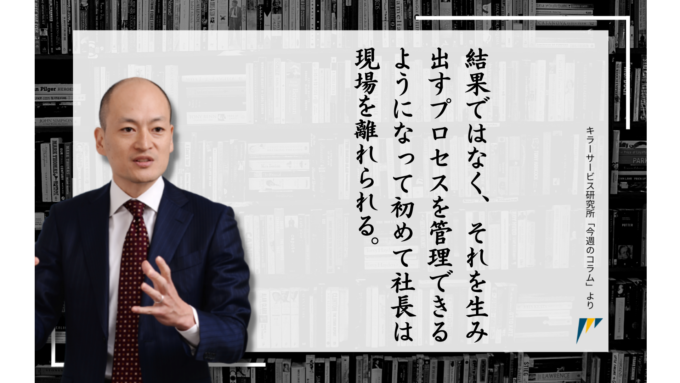
「結果だけ追いかけても意味がないっていうのはこういうことですね…」── クライアント先企業のKPIをどう設定するか議論していた際に、社長がこう口にされました。
KPIという言葉を聞いたことがないという経営者は今どきさすがにいないと思いますが、この言葉の理解と運用方法を正しく掴んでおられる方は案外少ないです。
この社長もこれまでKPIとして設定していたのは、売上や利益の年間目標を単に月別にしただけのものでした。
「KPI=業績管理指標」という日本語訳がこの誤解を引き起こしているのだと思いますが、業績というのはあくまで結果であり、経営者が結果をモニターすることなど当たり前ですから、それをKPIマネジメントと呼ぶのではありません。
本来KPIというのはKey Process Indecator つまり「重要プロセス指標」のことを指します。(最近は英語でもKPI=Key Performance Indicatorと言うことが多く、そこも誤解を生むポイントです)
プロセスというのは結果(ゴール)を生むための「過程」ですから、KPIも過程を表すものでないといけません。
たとえばダイエットしたいといって目標体重だけを決めて、それを実現するための行動を何もしないのであれば、経過体重をモニターしても意味がないということです。
ですからKPIマネジメントを行うためには、ゴールを実現するための戦略設計が必要になります。
ダイエットの場合ですと、痩せるために運動と糖質制限と断食をやると決めたとしたら、月間KPIは以下のようなものになります。
運動:ウォーキングをした回数(日数)や歩行距離、ジムに行った回数など
糖質制限:ご飯・パンを食べなかった食事回数
(↑敢えてこのように計測が簡単なものにする)
断食:一日断食を実施した日数
以上のように「いくら痩せたか?」ではなく、「痩せるための行動をどれだけやったか?」をモニターし、できていない場合は何らかの手をうつのがKPIマネジメントです。
上記はダイエットですので何をKPIに設定するかはそれほど難しくないですが、これが経営課題となるとそう簡単ではありません。
たとえば売上を上げるためには営業の活動量が大事だ!といって営業マンの顧客訪問回数をKPIに設定するのは短絡的です。なぜなら営業はただひたすら訪問すれば売れるというものではないからです。
特に法人営業の場合は購買決定権を持たない担当者と何回会ったところで案件は決まりませんから、決定権を持つキーマンとの商談の有無もKPIに含めます。
具体的には以下のようなプロセスの進捗を見える化するイメージです。
J:基本情報収集
I:テレアポ完了
H:初回訪問完了
G:キーマン把握
F:キーマンとの面談
E:キーマンへの提案完了
D:見積もり提出
C:見積もりのフィードバック受領
B:受注見込み確認
A:受注
このように各ターゲット顧客がいまどのプロセスまで進んでいるかを見える化して集計すれば、ゴール達成に向けて順調に進んでいるのかどうかを経営者が把握できるということです。(そういえば男女の関係の進捗もかつてはABCで表していましたね笑)
これは単なる一例ですが、当然ながら案件の中身によってたどるべきプロセスは異なりますから、案件ごとにKPIを設定する必要があります。
これは一見面倒臭いことのように思いますが、最初に正しいKPIを設定しておくことによって、いちいち部下に「あれどうなってる?」聞く必要がなくなります。(しかもその質問に対する答えは「ちゃんとやってます」といった曖昧なものになりがちです)
こういった行動の進捗をモニターする仕組みがあってはじめて経営者は現場を離れることができます。これもよく混同されがちですが、「任せる」ことと「放置する」ことは違います。現場を任せたとしてもちゃんと過程をウォッチし、異変があれば適時に介入する必要があります。
繰り返しになりますが、KPIの設定はゴール(事業目標)と、それを達成するための戦略・戦術が定まっていないとできません。逆に言うと、KPIマネジメントをしっかりおこなうことで戦略的に考える習慣もついてきます。
結果を追いかけるのではなくプロセスを追いかける── 当たり前のことですが、経営においては見落とされがちですので、自社のKPI設定状況を再確認されてみてください。
