【経営革新コラム】 儲かるキラーサービスをつくる社長の視点 第277話:感覚派の社長が陥りがちが落とし穴
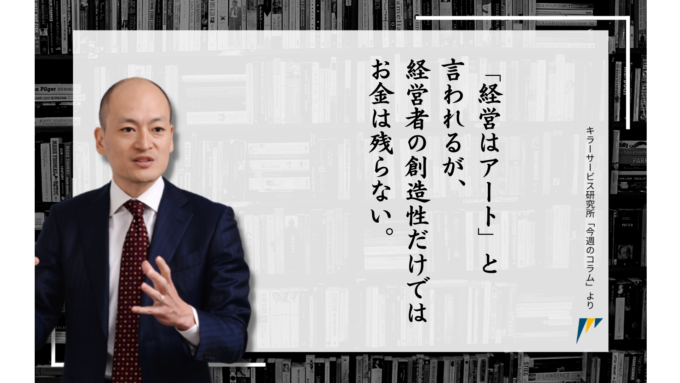
先日、元クライアント先の社長と3年ぶりに飲みに行きました。お酒がすっかり弱くなったとのことで少々ろれつが回らないながらも、「あの時うちに入ってもらってよかったですよ〜。私はとにかく感覚で決めるたちですからねえ…」と昔を回想されていました。
この方は自他ともに認める「感覚派」「感性型」タイプの方で、独特の世界観をお持ちです。人と違う発想で次々と面白いアイデアを出していかれます。
こういう方と話していると話が盛り上がって、新規ビジネスのネタもたくさん出てきたりします。自分もどちらかというと元々のベースは感性型の人間ですので、このタイプの経営者との会話は大好きです。
が、そういったタイプの社長がやってしまいがちなことがあります。それが、「仕組みづくり」を後回しにしてしまうことです。
私が20代の頃、まだ商社に勤務していた時代に参画した米国での新規事業では、米国人の社長が「超」が3つぐらい付くほどの感性型だったため、事業アイデアは素晴らしかったものの、見積もりは超ざっくり、顧客の要望は無料で安請け合い、現場オペレーションも社員任せで、「赤字を生み出すプロ」と化していました。
私は儲かる事業をつくるコツとして「外から見たらイレギュラー、中から見たらレギュラー」ということを提唱していますが、この経営者がやっていることは「全方位的にイレギュラー」だったため、会社にお金が残らず、最後は顧客にも迷惑をかける事態となったわけです。
このケースの失敗の原因は、この社長が感覚派だったからではなく、ちゃんと仕組みを作れる人間を登用しなかったことです。(当時の私にはその能力も権限も不足していました…)
昨今では「経営はアートだ」とか「経営は世界観が大事だ」といった言葉をよく目にしますが、アートだけでは経営は成り立ちません。(現に後世に名を残した芸術家であってもお金で苦労した人が大半です)
別の言い方をすると、アイデアや想いやビジョンといったものをいかにして「持続的な利益」に変えるか ── これが経営におけるアートであり、また我々のような経営の外部支援者が職人芸を発揮しどころであると思います。
これとは逆に、経営者が「論理型」の場合はいかにして「感覚派」の感性を取り入れて事業を面白いものにしていくかが事業発展の鍵となりますので、いずれにしても「弱い側面は補強する」ということが必要になります。
自社が感覚と論理のどちらに振れすぎていないか、ちゃんと事業アイデアを利益に変える仕組みが機能しているか、一度見直して見られてはいかがでしょうか。
