【経営革新コラム】 儲かるキラーサービスをつくる社長の視点 第135話: 社長が今一度考えるべき「企業の目的」とは
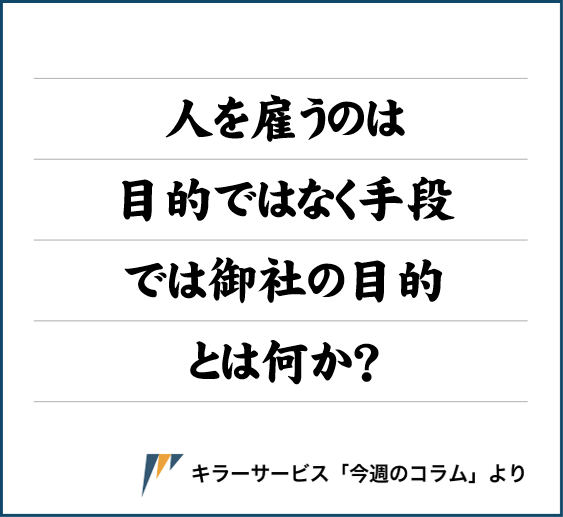
「会社っていうのは社員を雇ってなんぼですよねえ!」―― 先日、クライアント先の社長がお連れになったお知り合いの経営者の方が、話の流れの中でこうおっしゃいました。30人超の社員を抱えていらっしゃるとのことで、今後はさらに人を増やしていきたいと…。
社長同士の会話をお聞きしていて面白いなと思うことがあります。それは、自社の社員数で会社の大小を計り、それによって優先順位をつけられる方がまだまだいらっしゃるということです。「ほー、お宅は20人ですかー、ご立派ですな。うちは40人もおりますから、もう大変でしてー(笑)」といった具合です。
確かに、たくさんの社員を雇用され会社を回していくことは簡単なことではありません。基本的には人数が増えるほど管理が大変になりますから、一人一人に目が行き届かなくなると、物理学でいうエントロピー増大の法則にしたがい組織内部は乱雑さを増していきます。社員数が多いほど、組織で仕事を進める仕組みが必要となります。
しかしながら、だからといって社員数が多い会社の方が優れているということには当然なりません。いくら人数がいたところで、やっている事業に競争力がなければいずれは市場から淘汰されてしまいます。肝心なことは、その社員数によって会社として如何ほどの価値を生み出しているかです。
企業が「雇用」を継続するためには、当然ながら「利益」をあげる必要があります。「売上」ではありません。売上がいくらあっても利益が出ない事業はいずれ行き詰ります。利益こそが会社が存続するための源泉となります。
ではその「利益」の源泉は何かといえば、拙著「利益3倍化を実現する『儲かる特別ビジネス』のやり方」で詳しく書きましたが、これは他社がやっていることとの『差』ということになります。
この「差」をつくること、つまり「差別化」を実現することが利益を生むわけですが、この差別化というのは厄介なもので、『類似は差異に先立つ』と言われるように、「差を作っているつもりが結果的にはすごく似てしまう」ということが往々にして起こります。つまり本質的には他社と大差ない、という状態に陥ってしまうのです。
それがゆえに、顧客にとって一番わかりやすい「差」である「価格差」を泣く泣く提示することになってしまう…。『他社と違って何ができるか?』― ここがしっかりできていないと、結局は価格を下げて他社の既存顧客を奪うだけの商売となり、それでは売上は上がっても十分な利益がでず、雇用を守ることも難しくなってしまいます。
こうなると、きつい言い方になりますが「御社に存在価値がない」ということになります。
前回のコラムでドラッカー(および似非ドラッカーコンサルタント)について触れましたが、彼は企業の目的を「顧客の創造」と定義しました。これをまた「新規顧客を増やすことが大事」というように短絡的に捉える人が多いわけですが、前述のとおり他社の既存顧客を奪うだけではその企業に社会的な価値や意義は生まれません。
ドラッカーのいう「顧客の創造」というのは、御社にとって新しい顧客ということではありません。企業(あるいは事業)の目的は、「今まで世の中に存在しなかった新しい需要をもつ顧客をつくること」―― つまり、これまでにない新しいニーズ(市場)を創ること、ということです。
今すでに世の中にあるニーズというのは、AIによるビッグデータの解析によってすぐに明確になります。そして、そのニーズを満たすことは大企業があっさりやっていくことでしょう。中小企業がそこを狙っても苦しいだけです。
中小企業が生きる道は、いまだ顕在化していないニーズを創り出すことです。顧客のニーズを探ることではありません。新しいニーズを「捏造」するのです。これが企業の目的であり、真の「顧客の創造」となります。
そして、これを実現できるのが、当社が提唱している『特別ビジネス』です。競合も顧客もまだ気づいていない新しいニーズを満たす特別対応、イレギュラー対応を、社員が標準の仕組みでこなすことができれば、御社の存在自体が「特別」なものとなります。つまり御社の「目的」や「存在意義」が市場で認められることになります。
そのためには、顧客の声、つまり顧客が言っていることではなく、顧客が『言っていないこと』に着目する必要があります。彼らが何に気づいていないか、何を当たり前と思ってしまっているか、といったことに目を向けていく必要があるのです。
その具体的な方法については、当社が定期開催しているセミナーでお話していますが、大事なことは、「顧客ニーズの把握」や「競合分析」や「社員満足度の向上」…といった、経営にとって必要と世間が言っていることを、そのまま鵜呑みにしないということです。
御社独自の視点で、いままでにない戦い方をすることが、これからの時代に中小企業が存続するための鍵であり、御社が世の中に存在する「意味」となります。
