【経営革新コラム】 儲かるキラーサービスをつくる社長の視点 第137話:新しい時代に経営者がもつべき「ある思考の癖」
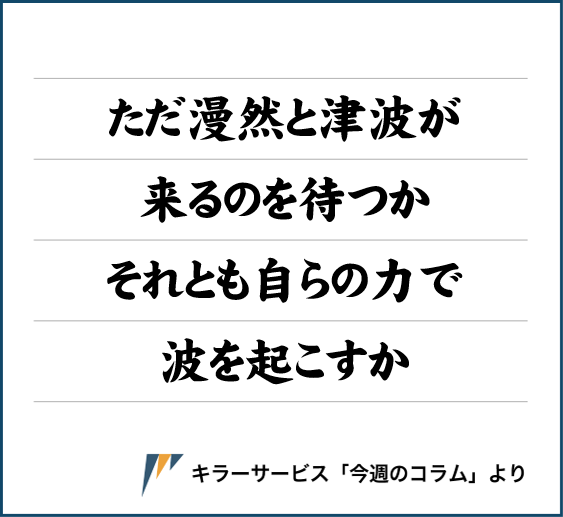
「日本はまだプラスチックストローがお店でも使われていますけど、これが欧州だったら大クレームですよ。日本人はおとなしすぎるんです。もっと声を上げないと…」― ある講演会で登壇者がこう語っていました。
日本人がおとなしすぎるかどうかは別として、確かに日本は歴史的に見ても、日本では大きな変化を外圧の力によって、ある意味いやおうなしに実現してきました。
日本の近代国家としての幕開けとなった明治維新も欧州からの後ろ盾と後押しで成し遂げられたと言われていますし、その後経済大国としての地位を築いたのも「敗戦」というすさまじい外圧によって持たされたものであることは否めません。
なぜ日本は外圧によってしか大きく変われないのでしょうか? 冒頭の登壇者が言うように日本人は大人しすぎるからなのか、それとも空気を読みすぎなのか、はたまた何なのか…。
この点に関して当社が考え、また危惧していることがあります。それは、われわれ日本人は、ビジネスにおいて非常に重要な「ある力」が弱い、あるいはその力を使う習慣が根付いていないということです。
その力とは、「現状を疑う力」です。
なんだ、そんなことか…そう思われたかもしれませんが、この「疑う」という習慣を持たないことが、いま日本がビジネスにおいて世界的に後れを取りつつ原因のひとつではないでしょうか。
冒頭のストローの問題に関しても、「このままプラスチック製品を使い続けたらまずいんじゃないか?」と欧州人は疑問に持ったわけです。そしてその疑問をリーダーシップをもって世に投げかけたからこそ、いまやグローバル企業が競ってプラスチックの使用廃止に向かう動きとなっています。
あまり「欧米は…」とか「日本は…」というように一般化して語りたくはありませんが、やはり傾向として日本は「周りの様子を見ながら、そろそろヤバいなというところで重い腰を上げる」というところがあります。つまり、自分から疑問を持つ、つまり問いを立てるのではなく、外から「答え」を示されることを待つという習慣が根強いのです。
これは国民性だと言ってしまえばそれまでなのですが、この根底には日本における教育の問題があります。戦後に確立されたいまの日本の教育方針をざっくり一言で言えば、「先生が答えを持っていて、生徒はそれを当てる(あるいはそれを覚える)」と言えるのではないでしょうか。
ちなみに欧米の教育スタイルはこのような「答え提供型」の要素は強くありません。大学の授業では先生は冒頭にある問いを投げかけ、それに対して生徒が自分の考えをぶつけていくスタイルが中心で、先生はその議論をファシリテーションし、議論を深める役目に徹しています。「なぜそう思うのか?」と、生徒により疑問を持たせていくのです。そして、授業の最後に先生が「正しい答え」を示すこともほぼなく、生徒各自の「問いを深め、自分なりの答えをもつ」― そんな力を養成していきます。
さらにいうと、欧米では大学以前の教育において、哲学を中心としたリベラルアーツの教育が組み込まれています。リベラルアーツについての説明は割愛しますが、一般に訳されている「一般教養」というよりは、世の中を正しく見る力を養うもので、それはそのまま「疑う力」の養成につながるものです。
戦後において、日本ではこういった「自分で考える力」、「現状を疑う力」、「自分で問いを立てる力」といった非常に重要な能力を鍛えるための教育は排除され、「上から答えを示し、それに従わせる」という、いわば骨抜きの教育が提供されてきたわけです。
さてここからが本題ですが、そういった教育に飼いならされてきたからと言って、それをそのままビジネスにおいてやってしまっては、これからの時代においては命取りとなります。
戦後の右肩上がりの時代においては、市場のニーズは非常に明確で、企業はとにかく顧客が望むものを一所懸命作っていれば経営が成り立った時代が長く続きました。もちろん競争はありましたが、それは基本的には「同じことを人よりうまくやる競争」でした。
しかし、今の時代のおいて、そんな明確なニーズを示されることはありません。「答えのない時代」と言われていますが、答えどころかどんな「問い」が投げかけられているのかも見えない時代です。
そんな今の時代において、経営者が絶対に持たなければいけない力というのが、この「現状を疑い、自ら問いを立てる力」にほかならないのです。
冒頭のストローの話と同様、「これって駄目なんじゃないか?」とか、「こっちの方がいんのではないか?」といった問いを自ら考え、市場・業界に対して投げかけていくことが、まさに企業が自社の存在意義を示すことにつながります。経営者は市場や業界に“NO”を突き付けることを求められているのです。
そこには、今まで自社がやってきたことに対する「自己否定」が必要になってくることもあるでしょう。今までせっせとストローを作ってきた会社が「ストローを使うのをやめよう!」を言い出すことなどは、まさに全面的な自己否定となります。
そんなことをやったら自殺行為じゃないか!と思われるかもしれませんが、では外圧による他殺の方がいいですか?という話です。自分から攻撃を仕掛ける方が当然ながら自分でコントロール権を握ることができます。新しいスタンダートをつくることができるのです。外から押し寄せる津波にさらわれるのではなく、自ら新しい波を起こすことが、まさに経営者に求められているのです。
そんな、現状を疑い、新しいスタンダードをつくる原動力として、企業の社長があらためて認識すべきことが、経営者としての自らの意識レベルです。ただ儲けようというのではなく、利益を出すことは企業として当然だとしても、その根底にどのような価値観や美意識、あるいは美学があるか。
経営者は論理的に戦略を立てることはもちろん必要ですが、それよりも「どんな意識で経営をするか」ということが問われる時代となりました。
皆さんは経営者として、何を疑い、どんな問いを世に投げかけますか?
