【経営革新コラム】 儲かるキラーサービスをつくる社長の視点 第175話:マニュアルづくりで失敗する企業の特徴
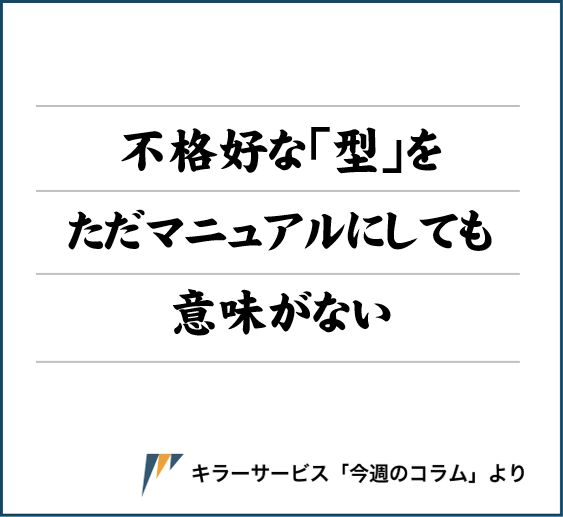
「来年の取り組みとして、ずっと先送りしてきたマニュアルづくりに着手したいと思います。お手伝いいただけますか?」── 継続して関わらせていただいているG社長からの依頼です。
「マニュアルをつくろうと言っても社員は動きませんから、やめた方がよろしいでしょう」とお伝えすると、G社長は「あれっ?」という表情を浮かべて続きを待たれます。
「マニュアルをつくろうと社員に伝えると、彼らはマニュアルをつくってしまうんですよ…」
社員に何かの取り組みをさせる場合に非常に重要になるのが、「その目的を理解させる」ということです。なぜそれをやる必要があるのか、それをしないとどうなってしまうのか、といったことを腹落ちさせる必要があります。
これは前々回のコラム『第173話:社長が知っておくべき「社員の目を輝かせる仕掛け」』でもお伝えしたことですが、そもそも人は現状に不満を持っていなければ新しいことに着手する動機を持ちません。現状に『痛み』を感じ、そこから逃れたいという欲求を持たなければ、基本的には現状維持の方に意識が向いてしまいます。
ここが大きな落とし穴で、よく社長が自社の「あるべき姿」を社員に語る場合がありますが、そのような「バラ色の未来(=快楽)」を社員に見せたところで、今すぐ動こうという気にはなかなかならないものです。
「確かにこのままではまずい」── 社員がそこを理解してはじめて、それを打破するための新しい施策をはじめる下地ができるわけですが、そのうえで社員には「その施策をはじめる目的」を正しく理解させる必要があります。
その点、「マニュアルづくり」というのは目的にはなり得ません。もし自社の仕事のやり方が、人によってバラバラだったり、毎回場当たり的な対応を繰り返していたり、うまくいくときもあれば行かないときもある…といった状態だとしたらどうでしょうか? その状態のままで表面的な「マニュアルづくり」に走ったとしたら、そのマニュアルはおそらく完成後も誰も活用しないただのごみと化すことは間違いありません。
マニュアルというのは単に「業務フローを書きあらわしたもの」、つまりアウトプットにすぎません。会議をやる目的はなにかを決めることであって、その議事録をつくること自体が目的とはならないように、大事なことは業務フローを良くするための「新しい仕組み」をつくることです。
さらに言うと、その仕組みづくり自体も目的とはなり得ません。仕組みづくりも手段であって、その仕組みを回すことによって「いままでできなかったことができるようになる」── これがあってはじめてやる意味が出てくるというものです。
納期を一日短縮したい
クレームを撲滅したい
技術指導を提供したい
若手社員でも現場を任せられるようにしたい
社員の頑張りを正当に評価したい…
そういった「目的」があってこその「仕組み化」そして「マニュアル化」となります。非常に当たり前のことを言っているようですが、ここが往々にして見落とされがちなのです。
当社が「その会社独自の強みづくり」と「それを実現する仕組みづくり」をともにご支援している理由もここにあります。仕組みづくりやマニュアルづくりを支援している機関は世の中に数多くありますが、「それによって何を実現したいか」── この内容がとんがっていないと何の意味もないからです。
会社で実施される多くの施策において「手段の目的化」が生じています。やはり動画だ! 広告だ! ブログも書かないと! 5Sも大事だ! ISOも必要だ! ERPだ! 研修だ!… それをやる目的や実現したいゴールについての検討が不十分のまま実施に踏み切るケースが後を絶ちません。
『何のために』
この重要なキーワードを社長は常に問いかける必要があります。ここが明確になれば、あとは最適な手段を選ぶだけです。きっと社員もついてきてくれます。
この「何のために」を突き詰めると、必ず意識は顧客を向きます。そもそもの事業の目的に思いをはせることになります。これが社員の視点を上げることにもつながります。そのような「外を向いた会社」が世の中を変えていきます。
社員が内向きなままで「マニュアルをつくろう!」とはじめても望む結果は得られません。「自分たちはなにを成し遂げたいか」── 社長はぜひ経営幹部とともにここの深掘りに向き合っていきましょう。
