【経営革新コラム】 儲かるキラーサービスをつくる社長の視点 第199話:会社批判を繰り返すミドルへの対処法
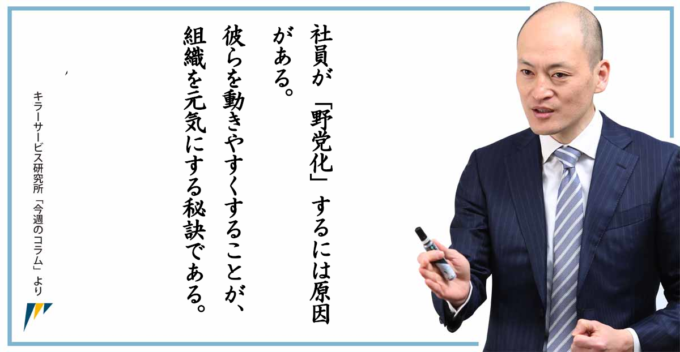
「うちは管理職が野党なんですよ。いつも会社の批判ばかりしていて…」― 製造業を営むS社長からため息がこぼれます。
当社がこれまで関わらせていただいた会社の多くも同じ問題を抱えていました。管理職が部下に会社の批判ばかりを伝え、肝心な会社の戦略や方針については放ったらかし…。最初はやる気に満ちていた若手も必然的に腐っていきます。
政治の世界では政府の横暴や行き過ぎにブレーキをかける野党の存在は必須ですが(これはこれで機能していませんが…)、ビジネスにおいては戦略の実行部隊として中核を担う存在のはずのミドルが会社批判ばかりではたまったものではありません。
なぜこのようなことが起こってしまうのか…。ひとことで言えば「ルサンチマン(弱者の逆恨み)」ということでしょう。経営トップがいかにわかっていないか、見えていないかを指摘することで、仕事で結果を出せない自分を正当化しているだけ。
仕事に真っ向から立ち向う自信もないし、そんなことをして自分が傷つくのも嫌。土俵の上に立って倒されるくらいなら、端っこからヤーヤー言っている方が安全だ…。
ここまで意識的に考えて野党化しているわけではないでしょうが、根底にはこのような心理が働いていることでしょう。
しかしながら、そんな彼らだけを責めるわけにはいきません。実は、ミドルが野党になってしまうのは彼らの性格や能力の問題だけではなく、往々にして「経営の仕組み」の問題だったりするからです。
つまり、彼らが野党になってしまうのは、「彼らが主役(与党)になれる仕組みになっていない」ということです。
そういうと「いやいや、ちゃんと彼らには責任を渡していますよ。基本的には彼らに任せると言っているのですから…」と言いたくなる社長もいらっしゃると思います。
なぜ彼らに任せると言っても彼らは動かないのか?
これには大きく2つの理由が挙げられます。
まずひとつめとして、「任せたことが大きすぎて、その社員の手に負えない」ということです。
たとえば、事業を丸ごと任せると言って責任を持たせても、その社員が事業責任者としてそれを全うする力量がない、という場合です。
事業を推進するとはどういうことかわからない。あるいは、やるべきことは頭ではわかっていても、責任が大きすぎて足が前に出ない、ということもあるでしょう。
一言でいうと「玉が大きすぎた」ということになります。
この場合、やるべきことはシンプルで、渡す玉を小さくすることです。その社員が「手に負える大きさ」まで仕事を分解して渡してやることで、その社員はとたんに自分が動くイメージが持てるようになります。
たとえば、事業を丸ごと渡すのではなく、まずは営業サイドだけに責任を持たせるとか、あるいはもっと小さくして新規顧客開拓だけをやらせてみるなど、事業を分解してその責任者をやらせるのです。そうすることで、彼に「自分の責任において何かを全うした」という実感を持たせることが大事です。
そして、任せた社員が動かない2つ目の理由としてあげられるのが、「彼にそれを全うするだけの権限や裁量がない」というものです。
たとえば、製造業においてある社員にひとつの事業を丸ごと任せたとします。そして、その事業を伸ばすためには自社の製造コストを下げることが必須だとしましょう。ところが、自社の製造部門は別の責任者(たとえば工場長など)がいて、その人物が製造についての権限を握っている、というような場合です。
この場合、ふたりがうまく協力し合ってことを進められればいいのですが、その製造責任者が反発したり、あるいは事業を任された人物が製造責任者に気を使ってしまったりして、やるべきことがなかなか実行されないということがよく起こります。
ここも経営者の出番です。任せた社員がその任務を全うできるよう、必要な権限を付与し社内にちゃんと知らしめることが必要になります。責任と権限は必ずセットで渡すということです。責任だけ渡して権限を渡さず「そこはなんとかしろ」では社員が動けません。ちゃんと戦える武器を渡してやることが肝要です。
上記の2つに共通して言えることですが、経営者はとにかくミドルが動きやすくなるよう「玉」をうまく設計することが非常に重要です。「玉」というのはつまるところ、事業のプロジェクトということになります。このプロジェクト運営をうまくやることで俄然ミドルが動きやすくなり、組織は元気になります。
プロジェクト運営の肝については当社が定期的に開催しているセミナーで詳しくお伝えしていますので、よろしければそちらも参考にしていただければと思いますが、とにかく重要な案件はプロジェクト化して、責任者を定め、適切な責任と権限を渡すことではじめて組織は機能します。
会社の批判を繰り返す野党社員も、心の奥底では自分が主役になりたいと思っているはずです。彼らが主体的に動ける経営の仕組みを構築し、彼らにスポットライトが当たるように仕向けていきましょう。
