【経営革新コラム】 儲かるキラーサービスをつくる社長の視点 第216話:社長が「考える」前にやるべきこと
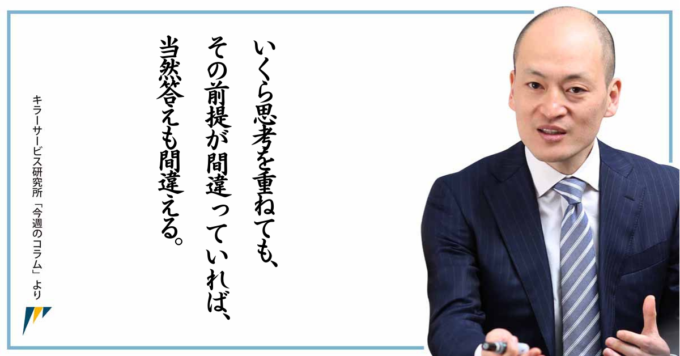
「社員に自分の頭で考えさせるというのは、本当に難しいことですねえ…」― 普段から懇意にさせていただいているお仲間の社長がしみじみこうおっしゃいました。
過去は社員がやるべきことについて常に詳細な指示を与えていたが、気がつくと皆が指示待ち人間になってしまっていたということで、最近は指示を出したいところをぐっと抑えて、一人一人がなにをすべきかを自分で考えるようにさせているとのこと。
経営において「考える」ことが重要であることはわざわざ言うまでもないことなのですが、では経営者が常にしっかり考えられているかというと、これはやはりそうではないわけで、考えるということは実に難しいものです。
岐阜の未来工業が「常に考える」というスローガンを社内の至るところに貼り出していることは有名ですが、同社のように社員一同が常に新しいアイデアを出していくような社内風土をつくるまでには、やはりステップバイステップで一歩ずつ進めていくしかありません。
その第一歩としては、当然ながら「まず社長が常に考える習慣を持つこと」が必要となります。もし社長が社員と同様に日常の業務(作業)に追われるような状態であったとしたら、落ち着いてじっくり考えることなどできません。
中小企業においては往々にして「社長がすべてやってしまう」状態になりがちですが、社長が「考える」ことに専念できる体制をつくるためには、社長は「自分に手足はない」ものと思って、社員でこなしていける仕組みを経営幹部とともにつくりあげることが必要ということです。
社長から社員までが毎日毎日もぐら叩きのように日常の問題をつぶしていくような状態からいち早く脱却し、日々の案件は社員だけでこなしていける仕組みを整えることが、まず社長がやるべき第一歩となります。
ここまでは過去の当コラムでも度々お伝えしていることですが、社長が「常に考える習慣」をもち、それを経営に生かしていただくために、「考える前にやっていただきたいこと」があります。
その「考える前にやること」とはなにかというと、それは「見ること」です。正しく考えるためは、「正しく見る」ことが必要になります。
人間の知的生産は「知覚→思考→実行」というプロセスをたどります。考える材料として「どのように状況を捉えるか?」との解釈がそのあとのプロセスに影響を与えるということです。
具体的に何を正しく見ることが大事なのか…。これはいろいろありますが、たとえば自社商品の競争力は正しく見えているでしょうか。人というのは無意識に自分の都合のいいものの見方をしてしまうものです。自社商品が一番競争力があると、盲目的に思い込んでいるケースは当社の支援先企業においてもよく見られた現象です。
自社の商品やサービスが本当に競争力があるのか、他社に比べて本当にいいものなのか、これを確かめるために、「見る」方法はいろいろとあります。
たとえば、顧客ヒアリングです。これは非常にオーソドックスなアプローチながら、ついつい怠ってしまいがちなことです。
顧客ヒアリングのポイントは「自社商品のコアユーザーだけにヒアリングしない」ということです。自社のファンはいいことしか言ってくれません。耳を傾けるべきは、離反顧客や他社品ユーザーの声です。彼らに対してグループヒアリングをしてみると、自社商品サービスについてびっくりするようなネガティブな意見が飛び出すことがあります。
あるいは、競合の商品・サービスを実際に買ってみる(体験してみる)ということも、意外とやっていない会社も多いです。自社の大口顧客から離反されてはじめて競合品を実際に見てみたということが実際のケースでも多々あります。
また、顧客や競合だけでなく、もちろん社内の状況も正確に捉える必要があります。現場をじっくり観察する、社員の声にじっくり傾ける、そういった、考えてみれば当たり前にとるべき時間がもし取れていないとしたら、これを機会によくよく社内を「見て」みてください。
その際に、社長として持っていただきたい視点があります。それは「疑う視点」です。実際に目や耳に入ってくるものを疑っていただきたいのです。
これはなにも「ひねくれた視点をもつ」ということではありません(笑)。社員がいまやっている仕事のやり方が本当に正しいのか、社員が信じていることが本当にそうなのか、そもそも自社でやっていることは続けていくべきことなのか…というように、「本当にそうか?」という視点を常に持ちながら現実を知覚するということです。
繰り返しとなりますが、人は物事を自分が見たいように見てしまう習性があります。人は誰でもなにかしらのメガネをかけてものを見てしまうのです。ですから、ひとつの物事をいろんな角度から見る必要があります。
ぜひ今日からでも自社事業の状況を正しく見るために、現地・現物にあたってみてください。ご自身の知覚力をフルに使って、「考える前に見る」を実践してみてください。きっと新しい収穫があるはずです。
