【経営革新コラム】 儲かるキラーサービスをつくる社長の視点 第217話:事業戦略を立てる上で絶対に欠かせない「経営の見える化」とは
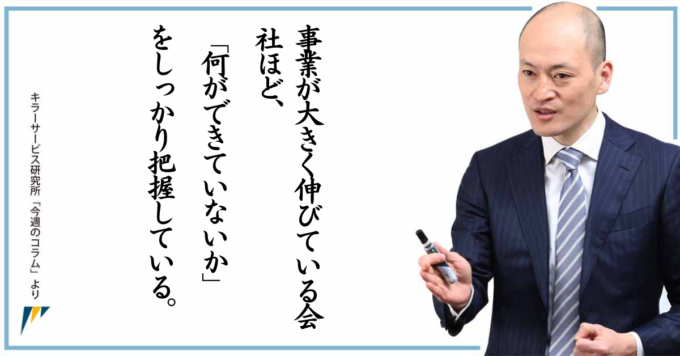
「実はそういうデータが見たいと思っていたんですけど、すぐ出てくるようになっていないんですよ。なんとかしないと…」― 商社を営むK社長の言葉です。
コンサルティング開始時に、現在の事業の実態を示す数字を伺ったのですが、K社長ご自身がまさにそういう数字を知る必要があると、モヤモヤされていたのでした。
もちろん、ここでいう数字とは試算表や資金繰り表といった経営数値のことではありません。そういった数字はK社長もしっかり管理をされて、数字にこだわる経営をされています。決して、よく言われる「どんぶり経営」になっているのではありません。
しかし、実際に経営戦略を立てるうえでは、もっと実際の事業の中身がわかる、具体的で生々しい数字を見て分析をする必要があります。
分析とは何をすることかというと、『分けて比べる』ということです。事業別の売上利益では見えてこない、もっと泥臭い実態を知るために、数字を分けて、並べて、比較し、そこから意味を見出す作業を分析といいます。
具体的にどのような数字の分け方をするかは、その事業によりけりではありますが、たとえば冒頭のK社長のような商社業で真っ先に見たいのが、仕入先別や商品別、あるいは営業マン別のアクティブ顧客数と、上位数十社の顧客名と売上金額です。
これらの数字で知りたいことを一言で言うと、「一体誰(どの顧客)が、何を、どれくらい買っているのか?」、そして「一体誰(どの営業マン)が、何を、どれくらい売っているのか?」ということになります。
同様に利益も確認します。商品別で営利まで出ていることが理想ですが、そこまでできていなければ、まず粗利だけでもいいので分析します。
分析とは「分けて比べる」ことですので、いろいろな切り口で数字を比較します。代表的な切り口は「時間」です。たとえば売上上位の顧客を昨年と今年で比較してみると、今年は「誰が買っていないか」がわかります。
あるいは上位顧客の商品別売上を過去と現在で比較してみると、いまは誰が「何を買っていないか」がわかったりします。
ある顧客に対する売上は昨年とほとんど変わっていないが、商品別に中身を見てみるとある商品だけ売れていないということがわかったとしたら、その商品は需要がなかったか、あるいは他社に取られた可能性がありますから、要深堀りということになります。
別の切り口としては「人」もあります。営業マン別の売上は当然どこの会社でも把握されていると思いますが、仕入先別や商品別の売上を営業マン毎に比較することでいろいろと実態が見えてきます。
たとえば、利益率の高いAという商品と、利益はあまり取れないBという商品があったとします。そして、営業部の佐藤氏はA商品をたくさん売っているが、鈴木氏はB商品ばかり売っているという事実がデータ分析からわかったとしたら、そこから深堀りする項目はたくさん出てきます。
もしかしたら、会社としては商品Aに拡販に注力すべきなのに、鈴木氏にはそれが(その重要性が)伝わっていないかもしれません。もしくは、商品Aの販売手法(営業トークや営業ツール)が、鈴木氏には共有されていない可能性もあります。あるいは、佐藤氏しか商品Aの仕入先との関係がつくれていないとか、そもそも商品Aの供給キャパが足りないとか、鈴木氏は商品Bの仕入先と仲がいいとか、いろんな可能性があります。
さらには実際の受注の数字だけでなく、営業マンごとの訪問社数や、新規先のテレアポ社数、見積もり提出数、見積もりの成約率といった数字を拾うことで、営業マンの行動内容についても実態を把握することができ、何ができて「いない」のかを知る手がかりとなります。
上記のように、具体的な数字を見て比較することで、うまくいっていることだけでなく、うまくいっていないこと、つまり、「何ができていないか」が明確になります。これは試算表の数字だけ見ていてもまったく見えてこないことです。何ができていないかがわかれば、自然と打ち手も決まってきます。
また、こういった具体的な数字は、経営者にとっての指標になるだけではありません。数字を様々な切り口で分解し、それらを社員に示すことではじめて、社員は事業の実態を「自分ごと」として捉えることができるようになります。
会社、あるいは事業全体の数字が上がった下がったと会議で伝えても、個々の社員は「痛み」を感じることができません。会社の業績が下がったところで、自分の給料や働き方には変化が出ないことがほとんどだからです。
これが、数字を分解し、個々の商品や顧客、社員別に実態に迫り、できていないことについて「なぜ」を繰り返すことで、ようやく個々の社員の中で「具体的な反省」が起きます。「自分もまずかった」と思えるようになります。
私もミスミ勤務時代に『個に迫れ』と、数字を分解して具体的に事業を論じることを徹底して求められました。そして実際に個に迫った実態把握から、戦略立案や事業立て直しの切り口を掴むことができました。
御社では、個に迫った実態把握からの戦略立案と社員の巻き込みができていますか? 最終結果の数字だけを見て、なんとなく打ち手を決めてしまっていませんか?
まずは自分たちのことを正しく理解するために、具体的な事実を押さえていきましょう。
