【経営革新コラム】 儲かるキラーサービスをつくる社長の視点 第219話:中小企業の社長が知っておくべき、本当のパワハラリスク
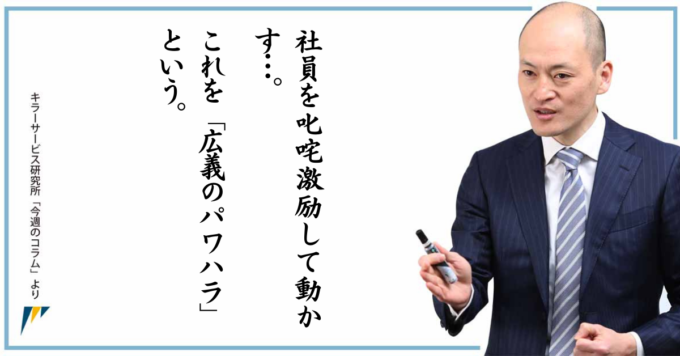
電通、トヨタ、三菱電機、パナソニック…昨今はこういった名だたる大企業においてパワハラの問題が表面化しています。暴力や暴言、あるいはありえない長時間労働などによって、社員が肉体的・精神的にダメージを負うケースです。
こういったパワハラ行為は昔からあったことでしょうが、2020年のいわゆるパワハラ防止法の施行などもあり、それがおかしいことだと声をあげられる機運が高まってきました。
パワハラで社員が自殺に追い込まれることなどということは言うまでもなくあってはならないことです。もしそういったことが自社で起こってしまったとしたら、まともな経営者であれば「経営上最大の危機」として対処に当たることでしょう。現に社員の自殺がパワハラ認定を受けたトヨタでは、章男社長自ら遺族に二度謝罪に出向いています。
そしてこのパワハラという問題は、いまや大企業に限らず中小企業においても「経営上最大の問題」となりつつあります。
それは、前述のパワハラ防止法が2022年4月から中小企業も対象になるから…というわけではありません。もっと別の理由で、中小企業の経営者はパワハラのリスクというものを真剣に考え対処する必要があるのです。
その理由については後述しますが、そもそも論として、自社でパワハラが起こっている(または起こる可能性がある)とは思っていない社長も多いのではないでしょうか。
ですが、実は多くの中小企業において実際にパワハラは起こっています。現に、「社員を採用しても定着せずにすぐ辞めてしまう」といった悩みをもつ社長は非常に多いですが、社員がすぐに辞めてしまうというのはパワハラが原因であることがほとんどだからです。
そう言うと、「そんなパワハラなんて大袈裟なあ。確かに若い子はすぐ辞めたりするけど、パワハラってわけじゃないでしょう」とおっしゃる方がほとんどだと思いますが、そこが実は落とし穴で、経営者は自社の経営リスクを正しく把握する必要があります。
確かに、法律にひっかかったり、社員から訴えられたりするような顕著なパワハラ(狭義のパワハラ)は起こっていない会社がほとんどでしょう。
しかしながら、なぜ社員がすぐに辞めてしまうかというと、多くの場合、結果が出せずに上司から叱咤叱責を受け続け、面白くなくて(あるいは耐えきれなくなって)辞めるのです。そしてこれは、広義の意味でパワハラと認識すべきなのです。
「いやいやそんな、上司ができない部下を叱っただけでパワハラなんて言われちゃあたまりませんよ」という声もあるでしょう。しかし、実際問題としてこの「広義のパワハラ」をなんとかしないと、中小企業はキツい罰を受けることになります。
それは法律による罰則ではありません。社員が定着しないということ自体が中小企業にとって非常に深刻なダメージになるということなのです。
大企業においては「せっかく入った会社だから辞めたくない」という意識が働いて、つらい状況を耐えて頑張る社員も多いことでしょう。(そして真面目に頑張りすぎて追い詰められるわけですが…)
しかし、中小企業の場合は社員にそこまで頑張りが効きません。すぐに辞める人は今後も増えるでしょう。なぜなら、他に就職先はいくらでもあるからです。
つまり、「いくら叱っても社員は成果をだせずに、いずれ辞めてしまう」という現象が起こっているとしたら、それは「経営上の大問題」と捉えてなんとかしないといけないということです。
ここで、なぜいくら上司が指導しても部下が成果を出せないのかという問題の根本原因をみる必要があります。なぜいくら指導しても成果が出せない社員が生まれるのか。それは結局「仕組みではなく、個人の力で仕事をしている」からです。いわゆる仕事の属人化です。
仕組みではなく個人の力に頼る仕事のやり方をすれば、そこには必ず個人差が出ます。みんなが同じ成果を出せるようにはなりません。そして、ほとんどの場合、指導する側の上司は個人の力が高いですから、できない人間の気持ちや抱えている問題が理解できず、指導が指導にならずにただ感情的に叱ることになりがちなのです。
そして、そういった現場では、「全体として結果が出ない→上司が部下を叱る→部下が萎縮する→ますます結果が出ない」という悪循環に陥ることになります。当然社内の雰囲気は悪く、叱る側、叱られる側双方にあきらめムードが漂います。
ここで言いたいことは、決して「社員が辞めないように優しく接しましょう!」ということではもちろんありません。個々の社員を指導する前に、会社として「成果が出る仕組み」を考えることが先ということをお伝えしたいのです。
リーダーの仕事は①誰でも廻せる仕組みを考える、②その仕組を社員が廻せるようトレーニングする、③組織として結果が出せるよう皆をフォローする、との三点です。この手順をすっとばして、部下に「ちゃんとやることやれよ!」と叱咤しても、社員はどう動いていいかわかりません。
特別な才能がない普通の社員でも廻せる仕組みを設計し、それを組織として実施していけば、管理者がチェックすべき対象はその仕組みそのものとなります。個人攻撃になりません。そうなれば社内は実にカラッとした雰囲気になります。
厳しい指導に耐えかねて辞めていく社員が多い会社は、「たまたま厳しい上司と辛抱が足りない部下がいた」のではないのです。組織全体を動かすシナリオが欠如しているのです。
根性論で弱者に厳しくあたる経営は破綻の道です。御社はそのリスクを回避できていますか?
