【経営革新コラム】 儲かるキラーサービスをつくる社長の視点 第233話:社長が立ち返るべき「商売のシンプルな原理原則」とは
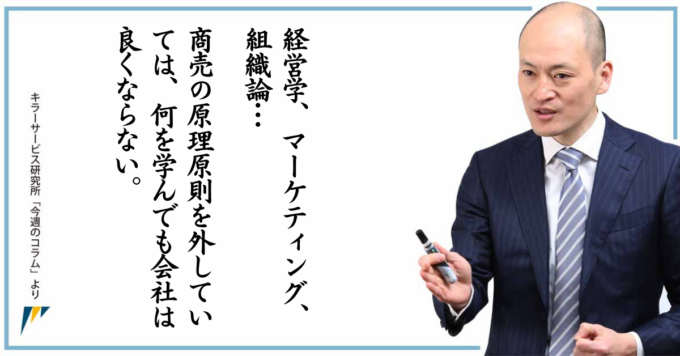
「おかげさまで商売の基本に立ち返ることができましたよ」── 2年ぶりに会った知人の経営者が拙著「儲かる特別ビジネスのやり方」を読んだ感想を聞かせてくれました。
「迷ったときに時々読み返しているけど、商売って結局シンプルなんですよね」
非常に嬉しい言葉です。実は同じようなコメントをクライアント先の経営者からいただくことがよくあるのですが、そういった方々は総じていろいろと勉強されてきた方が多いです。
中には著名なマーケターが主催するコミュニティに年間数百万も払い、数々のウェブマーケティングの手法を学んできた方もいらっしゃいました。
教えられたとおりに競合を分析し、自社のホームページやLP(ランディングページ)を作り直し、ウェブ広告も複数やり、さまざまなキャンペーンも実施して…。
散々いろんな手法を試した結果、この方は疲れてしまいました。「手法疲れ」といいましょうか。マーケティング手法を試しては結果に一喜一憂する日々に飽き飽きしてしまったのです。
なぜ疲れてしまうのか。それは「商売の本質からかけ離れていくから」です。
見込み客からの反応を上げようといろいろ試みるのはもちろん悪いことではありません。自社の差別化を図るために競合他社を研究することも時には必要でしょう。
ただし、それらは「いい商売」をする上での単なる手段のひとつです。そして、多くの方がそういった手段を目的化し、商売の本質から離れていきます。
では商売の本質とは何か? その答えは実に単純です。それは「お客様を喜ばすこと」です。
「そんなことはわかっているし、もっと多くのお客様に喜んでもらうために営業やマーケティングをやっているんじゃないか!」と言いたくなる方もいらっしゃるでしょう。
ですが、ビジネススキルをがんばって学んで実践している人が落とし穴に陥ります。意識が「他社との競争」に向いてしまうのです。その結果、顧客から意識が遠ざかっていきます。
他社との差別化を図ろうと業界を研究する中で、自分の中でできあがるもの、それが「常識」です。差別化もあくまでその「常識」の範囲内で行われます。差をつけようと同業他社を深く知れば知るほど似てしまう。差別化の罠です。
他社が何をやっていようとどうだっていいのです。一番大事なものは自らの世界観です。そしてその世界観は「顧客の役に立ちたい」と願う中で培われ磨かれていくものです。
何かで困っていたり、満たされないニーズを抱えていたりする目の前の顧客に対し、果たして自分は何ができるのか。それを考え抜き、実現させ、そしてお客様に喜んでいただく。それが商売の本質に他なりません。
そして、お客様を喜ばすことをつきつめれば、結果として自社の事業は他社とは差別化された事業の形になっているはずです。同業他社とどう差別化しようと考える思考とは無縁の世界です。
当社のクライアント企業においても、その経営者の「顧客に対する想い」でコンサルティングの結果に差が出ます。
顧客を喜ばせたい!助けたい!との想いが強い経営者は、業界の常識、自分たちの常識の殻を破って独自のビジネスを構想します。正確に言うと、殻を破ろうと必死で粘ります。私も意気に感じ、コンサルティング現場の温度は自然と高まります。
一方で、あくまで自分たちがやってきたことの延長線上の範囲内で考える経営者は、結局新しい事業構想も中途半端になります。ググったら出てくるような事業アイデアで手を打とうとします。コンサルティングも淡々と進みます。
うまくいっている同業他社のようになりたいのなら、船井総研にお願いすればよろしいでしょう。業界別に縦割りされた専門コンサルタントがその業界のお手本を示してくれるはずです。
そうじゃない!自分の世界観を突き詰めて、顧客が本当に喜ぶ顔をみたいんだ!という経営者はぜひ当社の門を叩いてください。ご自身が気づいていない、新しい自社の可能性を感じることができるはずです。
冒頭の経営者の言葉どおり、本日のコラムは「仕事」でも「ビジネス」でもなく「商売」という言葉を使いました。「いい商売」という言葉からはこちらも顧客もともに幸せになるような響きが感じられます。
売り手も買い手も儲かる── 本来商いとはそういうもののはずです。他社との競争で安値ジリ貧のビジネスになってしまっているとしたら、いま一度シンプルな商売の原則に立ち返りましょう。
商売は楽しいものであり、儲かるものです。
