【経営革新コラム】 儲かるキラーサービスをつくる社長の視点 第238話:儲かっている企業が例外なく習慣にしている「あること」
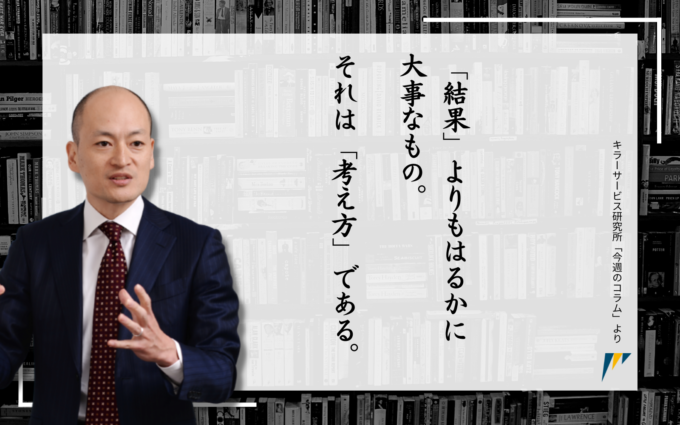
「ミスミさんが儲かっているのは知ってたけど、やっぱりそこまでやってるんですね…」
私が以前勤めていたミスミでは、中小企業も真似をすべき「儲かる仕組み」や「成長するための仕組み」が多々あるのですが、その内容を経営者にお伝えするたびに冒頭のような言葉が聞かれます。
つまり、「会社がうまくいくには理由がある」ということですが、これを逆にいうと「会社がうまくいかないのにも理由がある」ということになります。
すごく当たり前のことを言っているようですが、「うまくいっている会社ではどこも普通にやっているのに、うまくいっていない会社では全くそれがなされていない」ということは本当にいくつもあるものです。
なぜそんな「どこの会社もやるべき基本的なこと」がうまくいっていない会社で実行されないのかと疑問に感じる方も多いかもしれませんが、これは現実問題として「うまくいっている会社」から「うまくいっていない会社」への人材の流動が限定的なため、そのような「いい習慣」が伝承されないということでしょう。
ではその「うまくいっている会社」では必ず実行されていることの筆頭格をお伝えしたいと思いますが、それは「考え方の言語化」です。
「考え方の言語化? どういうこと?」と思われる人もいらっしゃるかもしれませんが、うまくいっている会社では何をするにしても必ずその「考え方」を考え、それをちゃんと文書にしているのです。
たとえば、外注先を起用しようと考えた場合でしたら、具体的に以下のような事項を考えます。
・外注先を起用する目的は?
・どのような場合に外注先を使うか?
・どんな外注先を起用すべきか? 最終的な採用基準は?
・外注先の管理はどうするか?(誰がどのようにやる?)
・外注先を起用する際のリスクは? その対応策は?
こういったことをしっかり考えて文書にまとめると、それが「方針書」となります。「方針書」とはつまり「何かをやるときの考え方」が文書にされたものです。新規獲得営業、既存顧客営業、マーケティング、人材採用、仕入れ、在庫…なにをやるにせよ「考え方の言語化」が必ず必要になります。
もちろん、上から下に方針を示す場合だけでなく、下に考えさえる場合も同様に文書で出させます。これが「提案書」です。うまくいっている会社では社員にもちゃんと考えさせて文書を書かせています。
「考え方」をしっかり考えていない会社には2つの特徴が見られます。ひとつは「場当たり的」です。答えに至るまでの議論が浅いため、その答えが当てずっぽうに近いものになります。「なぜ」が抜け落ちているのです。ですから、何をやるにしても成功確率や再現性が低くなります。
そしてもうひとつの特徴は「受け身」です。方針が決まっていないので、目の前の現象に振り回されます。自分の軸がないのです。社内でよく出てくる言葉は「ケースバイケース」「お客様次第」「状況による」といったものになります。
「場当たり的」で「受け身」の会社がうまくいくはずがないことは誰にでもわかることだと思います。経営者なら誰もがそんな状態を脱したいと望むことでしょう。であればすぐにでも「考え方を考える習慣」をつけていくことしかありません。
やり方は簡単です。社員が何をするにしても「それはどういう考え方?」と経営者が聞きまくればいいのです。私もミスミ時代に経営陣から毎日毎日「考え方」を嫌というほど聞かれました。
社員と「考え方」を議論し、結論を文書にまとめさせる。それだけです。そして、結果に一喜一憂せず「考え方」が正しかったのかどうかを振り返る。それを繰り返すことで、社員の考える力は必ずついてきます。
「考えること」は「書くこと」です。書かなければ考えたことにはなりません。必ず文書を起こさせる。これをやるかやらないかで会社は大きく変わります。やらない手はありません。
儲かっている会社の経営者ほど文書化の威力を知っています。
