【経営革新コラム】 儲かるキラーサービスをつくる社長の視点 第239話:経営者が知っておくべき「商品を売るために絶対に必要な2つのもの」
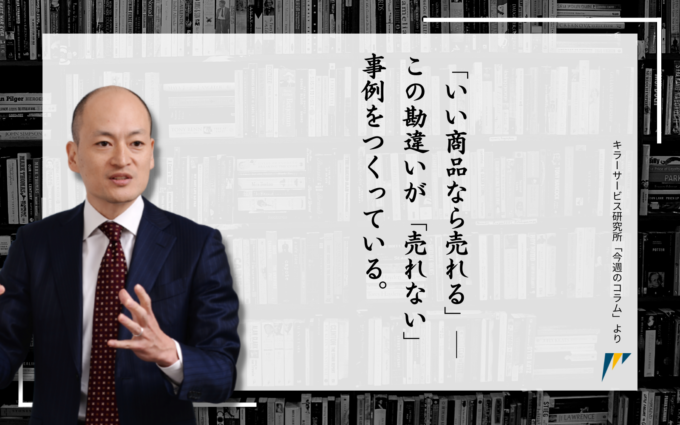
「商品は作ったものの、これをどうやって売ったらいいか全く見えてなくて…」── あるニッチな業界向けのソフトウェアを開発された方からのご相談です。
「まずは顧客のニーズを把握するために、見込み客とのつながりをつくっていこうとは思っています」というお腹が痛くなるようなセリフも出てきました。
(普通は見込み客のニーズぐらい商品をつくる前に把握するだろう…)と、きっと皆さんは思われることだと思いますが、このような「顧客が見えない商品開発」の失敗は実はめずらしいことではありません。
たとえば技術者や専門家(大学教授など)が商品を開発すると顧客そっちのけになりがちだったりします。
これはいわゆる「プロダクトアウト」ということになりますが、プロダクトアウト自体が悪いわけではありません。現に「プロダクトアウト」の逆の「マーケットイン」、つまり顧客ニーズを汲んだ商品開発の失敗例も山ほどあります。
なぜ顧客の声を聞いた商品開発がダメなのかというと、理由はいろいろありますが、端的にいうと「驚き」や「とんがり」が生まれないにくいからです。
顧客が「欲しい」とわかってる商品は、おそらくすでに世に出回っているものやそれに近いものの可能性が高く、いい意味で顧客の期待を裏切ることになりません。喫茶店でコーラを注文した顧客にただコーラを出すようなもので、いわば当たり前すぎるのです。
大ヒットする商品は顧客のニーズを汲んでいません。ヒット商品を出し続けている家電ベンチャーのバルミューダがいい例です。2万円以上もするトースターや4万円もするデスクライトを顧客が「欲しい」とは言っていなかったはずです。顧客は自分が本当に何が欲しいかを必ずしもわかっていないのです。
では結論は「マーケットイン」ではなく「プロダクトアウト」が正解か?というと、答えはNOとなります。やはり冒頭の例のような「顧客を知らない商品開発」ではダメなのです。
新しい商品やサービスを開発する場合に絶対に必要なのは、やはり「顧客起点」であることに変わりはありません。顧客をよく知ることなしに商品開発をするなど博打の度が過ぎるというものです。
では、顧客の顕在ニーズを直接的に満たしにいくのではなく、顧客の想像を超えた「新しい価値」を創りつつ、それがちゃんと顧客に売れるようにするためにはどうすればいいのか?
その答えは、事前にセールスの『ストーリー』と『導線』をつくっておくことです。
ここでいう「ストーリー」とは「顧客の心を動かすための筋書き」です。まだそのニーズに気づいていない相手に、「私がいま必要なものはこれだ」と思わせるシナリオです。
この「顧客の心を動かすストーリー」は、商品をつくってから(営業が)考えるものだという勘違いをしている経営者や開発者も少なくありませんが、それではそのストーリーが辻褄合わせのようなものになり「つくったけど売れない」といった事態になりがちです。セールスストーリーは商品を開発する際の中心の考え方になっていないといけないのです。
そしてもうひとつの「セールスの導線」に関しても事前に想定しておくべきものです。見込み客にどのように商品を認知させ、その必要性をどう教育するか。その道筋を事前に設計しておくことで、商品の完成後(あるいは完成前から)スムーズに販売活動を進めることができるというわけです。
これはなにも商品開発に限った話ではありません。自社で商品を開発しようがしまいが、企業が何かを売る場合には必ずセールスの「ストーリー」と「導線」が必要になります。例外はありません。
この2つの検討がおざなりにされる原因としては、やはり「いいものは売れるはず」という幻想があるのではないでしょうか。
まずはいい商品をつくる(仕入れる)。そして、どうやって売るかはできてから考える。 この順番で考えているから売れない事例が積み上がるのです。
売れる経営者は逆の発想をします。いい商品ではなく売れる商品を考える。つまり、どうやったら売れるかというストーリーが見える商品を探すということです。そして場合によってはその商品をつくる前に売ってしまいます。ストーリーと導線さえあれば商品はなくてもそれを売ることは可能ですが、その逆はないということです。
御社の商品について、それを売るためのセールスストーリーと販売の導線はつくられていますか? 商品そのものの価値ばかりに意識を向けていませんか?
お客様は商品そのものが欲しいのではありません。その商品を手に入れることによって自分がどうなるかという「筋書き」を待っているのです。それをイメージしたいのです。そして、それを見せるのは売り手である皆さんの役目です。
