【経営革新コラム】 儲かるキラーサービスをつくる社長の視点 第255話:「差別化」をやるとダメな理由
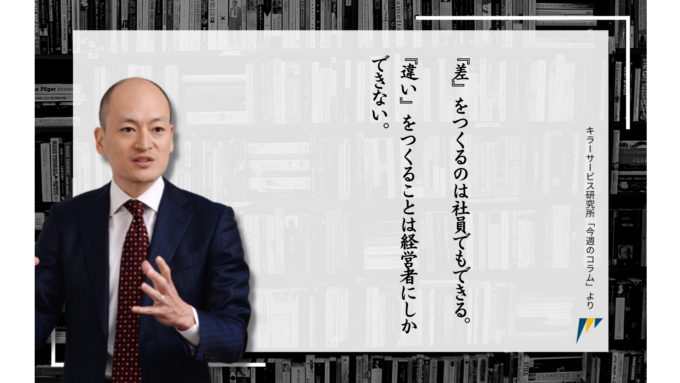
経営戦略をかじったことがある人ならマイケル・ポーターという人の名前は聞いたことがあると思います。ハーバード大の教授で、ざくっと言うと競争戦略理論というものをつくった人です。
そのポーターは1996年の寄稿文で「ほとんどの日本企業には戦略がない」と言い放ちました。80年代のイケイケだった時代が終わり、バブル崩壊でつまずいた日本企業に対して「ほらみろ」と言ってきたわけです。
アメリカ人にそんなことを言われるのは面白くはないですが、ただその後の日本の凋落ぶりをみると、同氏の指摘が的外れではなかったことを認めざるを得ないでしょう。
具体的に彼は日本についてこのように書いていました。
『ほとんどの日本企業は、互いにまねし、押し合いへし合いをしている。各社とも、ほぼあらゆる種類の製品、機能、サービスを提供しており、またあらゆる流通チャネルに対応し、どこの工場も同じようにつくられている。このような日本流の競争については、その危険性が理解され始めている』
「互いにまねし、押し合いへし合い…」── この指摘について「耳が痛い」とお感じになる経営者も多いのではないでしょうか。
そして、日本がこのような状態になりがちな背景として、ポーター氏は以下のように日本の文化的背景が要因と述べています。
『共倒れを招きかねない戦いから逃れようというのであれば、日本企業は戦略を学ばなければならない。そのためには、打破しがたい文化的障壁を乗り越える必要がある。
日本はコンセンサスを重視することで知られ、個人間の違いを強調するより、むしろ調整する傾向が強い。戦略には厳しい選択が求められる。日本人には顧客から出されたニーズすべてに応えるために全力を尽くすという、サービスの伝統が深く染みついている。
このようなやり方で競争している企業は、そのポジションがあいまいになり、あらゆる顧客にあらゆるものを提供するはめになる』
いかがでしょうか。日本企業の多くが必ずしもコンセンサスを重視しているがゆえに他社と同質化しているとは私は思いませんが、「顧客から出されたニーズに応えるために全力を尽くす」という指摘に当てはまる企業は非常に多いはずです。
顧客から出される要望の大半はQCD(品質・コスト・納期)に関することです。「もっと安くならないか」、「もっと早くならないか」といった要望に対応するため日本中の営業マンが忙殺されています。
品質を向上・安定させる。コストを下げる。納期を縮める。
このようなオペレーション改善(業務効率化)をオペレーショナル・エフェクティブネス(OE)と言ったりしますが、その努力の成果としてかつて多くの日本企業が世界トップに君臨しました。
そして、ポーターに言わせればオペレーション改善(OE)は「戦略」ではないということになります。なぜなら、それには「終わり(限界)」があるからです。
もちろんQCDも思いっきり突き詰めれば戦略的な競争優位性を持つことは可能です。たとえば私の前職のミスミは圧倒的なSKUを一気に標準化(自社規格化)して非常に強いポジションを築きました。工具販売のトラスコ中山も圧倒的な在庫カバー率で、アマゾンはもとより競合他社すら同社から買うような状態になっています。
しかしながら、他社よりも少し品質がいい、少し安い、少し早いといった状態を社員の頑張りで維持しようとしても、そのうち限界がきます。そしていつか追いつかれ、最終的には価格競争に巻き込まれてしまうのです。
では本当の意味で「戦略」とは何をすることを言うのか?
この答えを一言で言うと、『「差」ではなく「違い」をつくる』ということになります。
「差」というのは他社よりもベターという状態を指します。前述のような「他社よりも良い」という状態です。
そして、「違い」の意味するところは「比べられない特徴がある」ということです。これは「差」とは違います。
「差」ではなく「違い」をつくるのは経営者の仕事です。なぜなら「違い」をつくるためには「捨てる」ことが必要になってくるからです。つまり「何をやらないかを決める」ことが戦略を決める上で必ず必要となります。現に高収益企業の多くは「うちではそれはやらない」ということがはっきりしています。
前述のポーター氏の言葉にも『戦略には厳しい選択が求められる』とあります。これは社員では意思決定できません。これまでの流れや目の前の顧客のことを考えてしまうからです。
目先の利益をつくるためには必ずしも戦略は必要になりません。社員の動きの効率性や効果性を高めることは、管理者によるマネジメントによって実現できます。
しかしながら、企業が長期利益をつくっていくためには、単なる管理ではなく「戦略ストーリー」が必要になります。なぜうちは他社との競争に勝てるのか?との問いに答えるための論理(ロジック)が必要だということです。
子どもに「なんでお父さんの会社は勝てるの?」と聞かれたときに、「だってうちの会社は社員を死ぬほど働かせているからだよ」という答え以外の、シンプルで納得感のある答えが必要です。
その戦略的ポジショニングがあってはじめて、オペレーション改革(OE)も意味をなしてきます。
御社では根本的な「違い」をつくるための戦略ストーリーは機能していますか? 社員のがんばりで「差」をつくろうとしていませんか?
