【経営革新コラム】 儲かるキラーサービスをつくる社長の視点 第256話:文章を書けない経営者ではマズイ理由
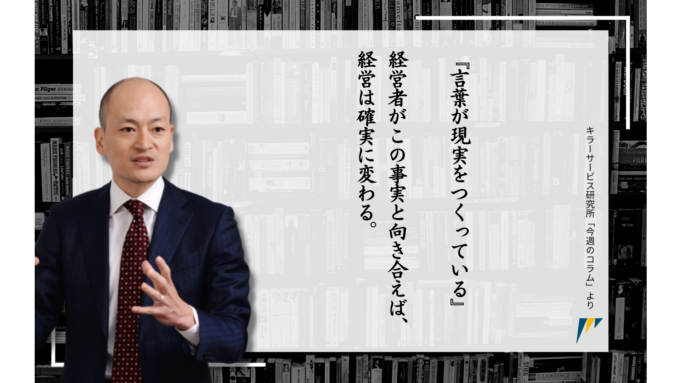
「いやあ、私はどうしても文章が苦手でして…」── クライアント先の経営者や幹部の方がこう口にされることが多いです。
ホームページや広告の文章、経営計画発表会でのプレゼン、採用候補者を対象とした会社説明会など…自社の事業内容などを言葉で説明する機会はなにかとあるものですが、そういった文章を書こうにもなかなか筆が進まないと。
たしかに「書くことが得意だから経営者になった」わけではないでしょうし、普段あまり文章を書くこともない方がほとんどでしょうから、経営者が書くことに苦手意識を持っていたとしてもおかしくはありません。
しかし、苦手だろうがなんだろうが、経営者は文章を書ける必要があります。その理由を一言で申し上げると「この世界は言葉でできているから」です。
「世界が言葉でできている」という概念は当コラムの長年の読者であればお馴染みのコンセプトだと思いますが、この世界は物質ではなく言葉でつくられています。
たとえば、いま私の目の前にはガラスのコップに入った「水」があります。この「水」が何でできているかというと、これも言葉です。水素と炭素ではありません。なぜなら、「水(みず)」という言葉を私たちが持たなければ、私たちはそれを「水」と呼ぶことはできません。
「いや、たとえ言葉がなくて「水」と呼べなくても、水はそこにあるだろう」と思われるかもしれませんが、では「ある」という言葉がなくなったらどうなるでしょうか。「水」「飲み物」「液体」「コップ」「入れ物」「ある」「そこに」といった言葉が存在しないとしたら、目の前にある「水」は消滅してしまうのです。
「いやいや、消滅するわけないでしょ」とまだ思われるかもしれませんが(笑)、それではこれはどうでしょう。「蛾(が)」という生き物はご存じですよね? そう、あの蝶々に似た、人に嫌がられる昆虫です。
あの「蛾」ですが、フランスやドイツには存在しないのをご存じでしょうか? いや、ほかにも世界数十カ国で「蛾」は存在しないそうです。なぜなら、そういった国々では「蝶」も「蛾」も同じ言葉で表すからです。(フランスの図鑑には蝶(パピヨン)のページに蝶と蛾が入り混じって載っています)
なぜこんな話をしているかというと、「水」も「蛾」も言葉でできているならば、御社の事業も商品もサービスもすべて『言葉』でできている、ということがいいたいのです。
御社の商品と他社品との違いも当然「言葉」でできています。
見込み客が御社の商品を買う理由も当然「言葉」でできています。
どんな人や会社がうちの商品を買うべきかー それも「言葉」が表現します。
自社の社員がどのような価値観を持つべきかー これも当然「言葉」で示されます。
経営理念、事業戦略、仕事の仕組み、社員の役割、ルールと権限、業務の手順、方針、考え方…経営に必要なものはすべて言葉でてきているのですから、経営者は「言葉を紡ぐこと」に強くならなければいけないのです。
世界中で売れまくった『サピエンス全史』によると、我々の祖先であるホモ・サピエンスが厳しい生存競争を勝ち抜けた要因は、彼らが「現実には存在しない虚構(フィクション)を語ることができた」からだといいます。
虚構というのは「いま目の前にないもの」ですから、先ほどあげた「理念」も「戦略」も「方針」も虚構ということになります。
そのような「無形」のものを「言葉」で語ったことにより、各自が「イメージ」を持つことができ、皆が協力して「生きるための仕事」に取り組むことができたということなのです。
これは現代に生きる我々にも同じことがいえます。企業は常に生存競争にさらされています。社員は一致団結して自社の「目的」のために力を合わせ、そして顧客を巻き込み、実際の現象を起こしていかなければなりません。
そのためには、リーダーの「言葉」が必要なのです。自分たちが誰で、誰のために何をしているのか。それを言葉で伝える必要があります。
もし、いま皆さんが持っている言葉では、他社との「違い」をつくるために十分ではないとしたら、まずはその言葉(虚構)を構想するところから始めましょう。それなくして現実は成立しません。「まず言葉ありき」です。
「顧客を動かす言葉」や「社員を動かす言葉」ー それ自体が御社の商品(売り物)です。事業者は例外なく言葉を売っているのです。
皆さんの売り物は明確になっていますか?
