【経営革新コラム】 儲かるキラーサービスをつくる社長の視点 第262話:元気な中小企業をつくるための2つの施策
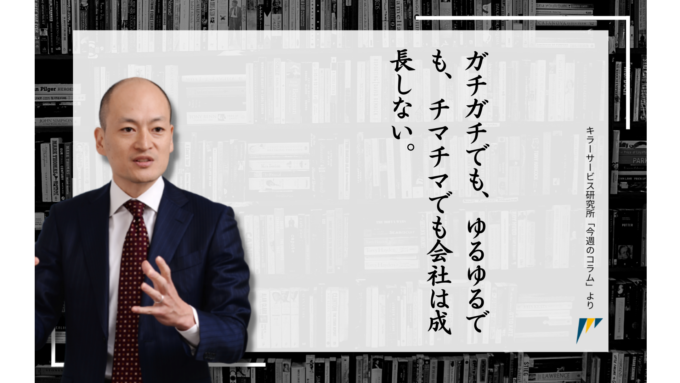
「中小企業って苦しいですよね。大企業と比べると人の質とか仕事のやり方とか全然違うでしょう?」── お仲間の社長と一杯やっているときに出た言葉です。
その社長は前職で中堅商社に勤めたのちに家業を引き継がれたのですが、中堅と中小でもこんなに違うのに、大企業と中小だとその差はとてつもなく大きいのでは?と疑問を持たれたわけです。
確かに、大企業と中小企業では社員の生産性にかなりの差があります。財務省の調査では、従業員一人あたりの労働生産性は大企業と中小企業で3倍程度の差が出ていますし、私の感覚的にもそれぐらい開いても不思議ではないなと思います。
なぜそんなに差がついてしまうのかというと、というと、やはり「人・モノ・金」の差が大きいでしょう。大企業はブランド力や資金力から人の確保も容易になりますし、商品開発やマーケティングにも金をかけられます。事業で少々コケても会社が倒れない体力がありますから、新しいことに挑戦するハードルも中小に比べると低いです。
持てる武器が限られている中小企業としては、そんな大企業とはなるべく戦いたくないところでありますが、実際はなかなかそうはいきません。過去は大企業と中小企業のテリトリーは割とはっきりしていましたが、昨今ではたとえば「地場の業者よりも大企業のウェブで頼む方が納期が早い」といった現象も普通に起きており、その境界線は非常に曖昧になってきています。
そんな、「地域密着」や「小回りのよさ」だけでは戦えなくなりつつある中小企業ですが、実は大企業ではなかなか生かしにくい「ある力」があります。
それは社員の「個の力」です。つまり社員一人一人の個性を生かすということです。
もちろんこれは、大企業には個性的な社員が少ないということではありません。ただ大企業では、その個性は抑制される傾向にあります。なぜなら、大企業では仕事のやり方や手順が確立されており、型にはまったやり方で仕事が進められる側面が強いからです。
そしてこれは悪いことではありません。ある意味「誰でも一定の結果が出せる」ところが大企業の強みと言えますし、中小企業も業務を仕組化・標準化して再現性を高める努力をすべきであることは、過去の当コラムでも散々お伝えしているとおりです。
しかしながら、ブランド力でも資金力でも商品力でも社員の能力水準でも劣る中小企業が大企業と勝負をしようと思ったら、これはもう「社員の個性を出しまくる」しか手がありません。彼らの個性を丸めるのではなく、むしろとんがらせる方に振れるのです。
個性の発揮しどころとしては、たとえば商品開発です。キャンプ用品メーカーのスノーピークは「キャンプ好き」が集まっていることで有名ですが、同社の商品開発には社員の「こんなのが欲しい!」という気持ちがダイレクトに反映されています。
これはB to Cの例なのでわかりやすいと思いますが、B to Bでも同じことです。担当者の「こんなものをつくりたい!」とか「売りたい!」という気持ちをできるだけ取り入れることで、社員の頭の中に「好き」のアンテナが立つことになります。
あるいは営業においてもそうです。もちろん身だしなみや言葉遣いなどにおいてマイナスポイントがあってはいけませんが、それはクリアした上で、他の営業マンがやらないような営業手法を取り入れることは全然「あり」です。
たとえば、自社の商品のことは一切語らず、自分が考える業界の未来構想についてひたすら語るとか。相手は商品の話は興味がなくても、自分の属する業界については少なからず関心があるはずなので、業界の未来について普通の人が語らないような話をすると一目置かれることでしょう。
言うなれば「商品を売らずに世界観を売る」アプローチ。これならば、飼い慣らされた大企業の社員に勝つ見込みは大いにあります。
上記はほんの一例ですが、社員の「個」を生かす切り口はさまざまありますので、中小企業経営者はぜひ自社の個性作りについて考えてみていただきたいと思います。
…が、ここで一点注意すべきことがあります。
それは『「個を生かす」ことと「個人任せにする」ことは全然違う』ということです。
よく「戦略とは捨てること」といいますが、人・モノ・金に限りがある中小企業において、あれもこれもといろんなことをやってしまっては、結局どれも成果が出ないということになりがちです。
いま会社として何に集中すべきかは経営者が方針を決めてトップダウンで落とす必要があります。これを「戦略的束ね」といいます。
戦略的束ねがないと、社員はバラバラな動きをすることになります。たとえば会社としては新規開拓をやらないといけない状況であるのにもかかわらず、営業マンに「既存ばっかり行かないで新規もやれよ」なんて言ったところで彼らがやってくれるはずがありません。
製造業で品質不良が非常に問題になっている場合なども同様で、対策を社員任せにしてしまっては、「目視で全品検査する」といった非常に時間とコストがかかるやり方を選択してしまったり、あるいは逆に「単なる心掛け」程度の対策に終わってしまったりと、経営者の意図と現場の動きが乖離してしまいます。
また、個人任せにしてしまうと「チマチマ病」に陥ります。発想が社員の裁量の範囲にとどまってしまい、思い切った手が打てていない状態になります。思い切って設備投資をするとか、組織体制を刷新するとか、新しい分野に打って出るとか、海外に進出するといったことは社員に任せていては成しえません。
事業の重要課題については経営者が明確に方針を決めて社員に落とし込む。その上で社員にも裁量を与えて自由に個性を発揮させる。このバランスが元気な企業をつくるポイントです。ガチガチでもゆるゆるでも駄目ということです。
御社は社員が重要課題に集中できるよう「戦略的束ね」を効かせていますか?
その上で彼らを「道具」としてではなく「血の通った人間」として生かせていますか?
