【経営革新コラム】 儲かるキラーサービスをつくる社長の視点 第274話:「社員が育たない」と悩む社長が見落としていること
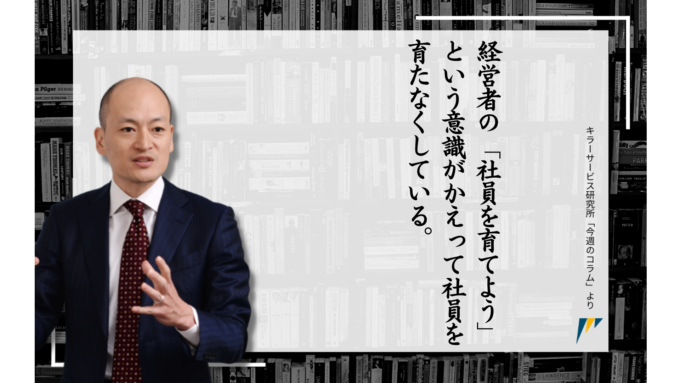
GW中は京都に帰省して高校の同窓会に出席しました。同窓生には社長や企業の役員をやっている人間も多いのですが、彼らが口を揃えて「社員が育たん…」と言っていたのが印象的でした。(高校の時にはこんな会話は出なかったので。笑)
確かに「社員が育たない」というのは経営者がもつ悩みの中でも一二を争うものでしょう。その証拠に世の中には「人材育成」をテーマとした研修やコンサルティングが山ほど存在します。
しかしながら、「社員が育たない=社員育成(のやり方)の問題」と考えるのは少々短絡的です。というのも、社員が育たないのは社員育成とは別のところに真の問題があるということが多々あるからです。
たとえばこんな問題です。
(1)事業戦略が機能していない
事業戦略の筋が悪く、競合との安値競争に明け暮れているような状態だと、どんないい人材でもやがてやる気を失っていきます。
「いや、そこ(戦略)の問題も考えるのがいい人材というものでしょう」と思いたい社長もいるかもしれませんが、そこは高望みが過ぎるというもの。そこはやはり経営者が担うべき領域です。
地面を掘ればゴールドがざっくさく採れる土地(=市場)に人を放てば誰でも目の色を変えて頑張るでしょうが、掘っても掘っても何も出てこないというのでは「もっと工夫しよう」とか「もっと成長しよう」なんて誰も考えないはずです。
かつてミスミの社長の三枝氏も「成長事業でしか人は育たない」と言っていましたが、人を育成する前にまず「儲かる事業モデル」になっているのかどうかを確認する必要があります。
(2)頑張っても報われない社内体制
前述の「ゴールドがざっくざく採れる土地」で事業をやって収益があがったとしても、実際に動いている社員がその果実を受け取れないとしたら社員はやってられないでしょう。
これは評価制度や報酬体系の問題もありますが、特に中小企業においては「硬直した人事」が問題になることも多いです。「いくら頑張っても上司を追い越すことはできない」というのでは優秀な人ほど辞めていきます。やはり「信賞必罰」が人を使うための基本であり、現に成長企業では「抜擢人事」が日常的に起こります。
(3)採用のミス
そもそも間違った人を採用しちゃってるというケースですが、ここで重要なのが、間違った人というのは「できない社員」ではなく「合わない社員」ということです。つまり会社や社長の方向性や価値観とそもそも合ってない人を採っている場合、その社員を育てようといろいろやっても機能しない可能性が高いです。
これを避けるためには、経営者の「いい人を採りたい!」という意識から「合わない人は採らない!」との意識転換が必要ですが、そもそも「自社の方向性や目指すゴール」が明確になっていないとどんな人を採るべきか(かつ採らないべきか)も見えてこないので、結局「組織は戦略に従う」というところに帰結するということになります。
以上のように「人の問題」と思っていることが、実は「システム」の問題だということが多々あります。経営者はつい自分の前の前にいる「てきない社員」に意識を向けがちですが、そんな社員をどうこうしようとするのは部分最適の最たるものです。
個々の社員が優秀だからといって必ずしも事業そのものが強くなるわけではありません。企業が長期的利益を生み出すためには、成果を出すための「再現性のある仕組み」をつくる必要があり、その仕組みこそが結果的に社員を育てることになります。
もし経営者が一部の「できない社員」に意識を取られているとすれば、それは会社にとって大きな損失です。
