【経営革新コラム】 儲かるキラーサービスをつくる社長の視点 第275話:経営の舵取りに必ず必要な「社長の切断力」
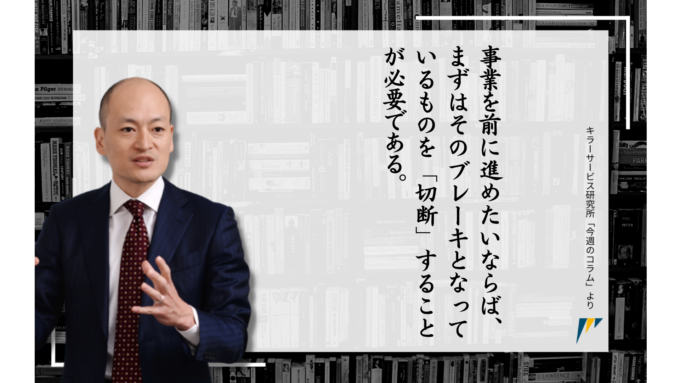
これまで中小企業の事業成長支援を続けてきて思うことですが、経営者が持つべき最も重要な能力のひとつが「切断力」ではないかと思います。
イノベーションや価値創造といった言葉に代表されるように、経営やビジネスの文脈でよく「何かを生み出す」ことが重要視されますが、実は生み出す前に「断ち切る」ことが先に必要になることが多く、「断ち切れないから生み出せない」という状況に陥っているケースがよくあります。
では何を断ち切ることが必要かというと、たとえば以下のようなものが挙げられるでしょう。
①「不採算事業・商品・顧客」
やってもやっても儲からない事業や商品をずっと持ち続けたり、あるいは全然儲けさせてくれない顧客とずっと商売し続けている会社は多いです。
「昔は売れた」とか「以前はよく儲けさせてくれた」とか、「祖業だから思い入れがある」といった理由でやり続け赤字を出し続けるわけですが、赤字は将来芽が出る可能性がある「楽しみな赤字」でない限りさっさと切り捨てるのが原則です。
あと、これもよくあるのが、実は赤字商品・赤字顧客であるのに原価計算が曖昧なために儲かっていると勘違いしているケースです。これは不幸で、営業マンがせっせと頑張って売れば売るほど赤字になるというなんとも気の毒なことが起こります。
この原価計算は経営上非常に大事なのですが、中小企業でちゃんとやっているところは思いのほか少なく、安売りするための「都合のいい原価計算」になってしまっていることも多いので注意が必要です。
②「合わない社員」
以前の投稿でも書きましたが、「できない社員」は鍛える余地もありますが、「合わない社員」を雇い続けてもいいことはありません。また、特に日本では「社員を辞めさせることは悪いこと」という認識をもつ経営者が多いですが、実は他の会社に移ってもらった方がその当人も結果的に幸せになる可能性が高いので、その人のためにも退職を勧めるべきでしょう。
合わない社員を会社に置いておくことの一番の弊害は、その社員のことで社長の「脳内キャパ」が食われてしまうことです。その社員のことで悩んだり怒ったりしても会社は1ミリもよくならないですし、社長はほかに考えるべきことがたくさんあるわけですから、社長が社長の仕事をするためにも合わない社員とはさよならすべきです。
少なくとも「合わない社員には辞めてもらう」と決めることで、「ではうちに合わない社員とはどのような人か?」との問いを考えることにもなりますので、そのような意識で社員と向き合うことです。
③「欲」
いきなり抽象度が上がりますが、結局「欲」が人の判断を狂わせます。たとえば「なまけたい」という欲が事業の「現状維持」という方針(?)を取ることに繋がったり、「ラクして儲けたい」という気持ちから「誰でも儲かる」という筋の悪い事業に手を出してしまったり…。
もちろん、事業は儲けるため(利益を出すため)にやることですし、かく言う私自身が「儲かる手法」を売っている人間ですので、経営者の「儲けたい!」という気持ち(欲)を否定するものではありませんが、そっちに振れすぎるとバランスを欠いてかえって儲からなくなりますので、その欲を「志」に昇華させることが重要です。(「論語と算盤」ですね)
昔の武士も「断ち切る」ということを何より重視したために、帯同する刀を「太刀(たち)」と呼んだとか。勝ちたいという欲が焦りや力みを生んで、結果勝てなくなるということですね。
「不安」や「恐れ」も結局「失敗したくない」「会社を潰したくない」「死にたくない」といった「欲」から生まれますが、その「欲」に自らが振り回されてしまうと本末転倒でかえって欲が満たされないということにつながります。
一方で、過剰な欲(感情)を断ち切り、ロジック(論理)で判断することで、経営者として本当にやるべきことも見えてきます。
我々は侍のように太刀は帯同していませんが、不要なものはいつでも断ち切れる精神を保っていきたいものです。
