【経営革新コラム】 儲かるキラーサービスをつくる社長の視点 第278話:高収益企業になるための「粗利率の意識改革」
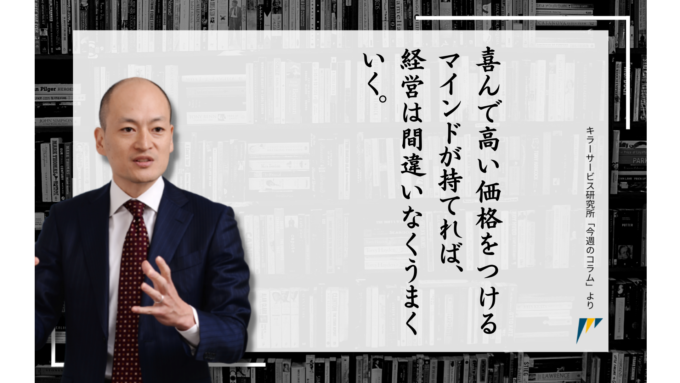
「粗利率60%! うちには到底ありえない数字ですねえ…」── 先日コンサルティングをスタートされた精密加工業のY社長がため息混じりにおっしゃいました。
私の前職であるミスミの話をお伝えしたときのことですが、同じ製造業でどうやってそんな利益率になるんだと驚かれていました。
企業の利益率においてよく注目されるのは「営業利益」や「経常利益」ですが、経営者がもっとも注目すべき利益率は「粗利率(売上総利益率)」です。なぜなら、粗利率は「事業そのものの強さ」をあらわすからです。
粗利率が高いということは、それだけ顧客に対して付加価値を生み出せているということになります。つまり、自社の提供する商品やサービスによって顧客が恩恵を受ける度合いが高いため、値段が高くても顧客は買ってくれるのです。
この粗利率に関していうと、世の中には2種類の経営者が存在します。それは「粗利率を上げようとする経営者」と「下げようとする経営者」です。
利益率は高い方がいいに決まっているのに「粗利率を下げようとする経営者」が存在するのか? と思われるかもしれませんが、実際にはそのような経営者の方が多いのではないでしょうか。
「粗利率を下げようとする」とは簡単に言うと「安い値段で受注を取ろうとする」ということです。
これに関しては「うちはそんなに安い値段は出してないよ。競合の価格帯とだいたい同じくらいで出している」という方が非常に多いと思います。
しかしながら、競合と同じ価格帯になっているということは、結局は競合からの「価格プレッシャー」があるということですから、値段は下がる傾向にあります。ベクトルとしては「粗利率を下げようとする動き」になっているのです。
「そうは言っても、やっぱり競合と比べられるからこれ以上高い価格はつけられないよ」と思う経営者が世の中の大半だと思います。そして、このような考えの経営者にとっては「(他社よりも)価格が高い=悪」となります。
ところが、「うちは他社よりも高い価格を出そう」と意図的に高値を出す経営者も一定の割合でいらっしゃいます。これが「粗利率を上げようとする経営者」です。
このタイプの経営者の代表例はキーエンスの滝崎会長でしょう。滝崎氏は創業一貫して「付加価値(つまり粗利)が8割を下回る製品は売らない」とのポリシーを貫いているといいます。
この境地までいくと日本を代表する企業への道が拓けるのですが、ここまでいかなくても高収益を出している企業の経営者のマインドとして共通していることは「安いものはやらない」ということです。
こう聞くと「うちだってそうしたいけど、そんな高い値段が通るような強みや特徴はうちにはないし…」と思う経営者が多いと思いますが、「粗利率を上げる経営者」はそうは考えません。
彼らの思考パターンは、まず「値段は高くする」ということを決めて、そこから「じゃあどうしようか」と考えるという順番をとります。つまり、当コラムで度々お伝えしている『切断力』を発揮して、「安いものはやらない」と決めることから出発しているということです。
安いものはできないのですから、何か他社と違うことをやるしかありません。必然的にその企業は「特別ビジネス」をやることになります。
私の著書でもご紹介した「でんかのヤマグチ」の山口社長も、過当競争から生き延びるために「粗利率を上げる経営者」になることを決断されました。営業マンの電卓の「÷」「6」「5」のキーをマジックで赤く塗らせ、「これからは見積もり時に35%のせろ!」と指示を出したそうです。
「そんなの絶対無理です!」と訴える営業マンに対して社長は「じゃあどうすれば35%取れるのか考えろ」と。
そのように社長から退路を絶たれた営業マンたちは、顧客数を絞り、いつでも駆けつけられる顧客に対して「至れり尽せり」の対応をすることで価格を上げていき、8年後に全社粗利35%を達成しました。
ここで言いたいことは、まず「粗利率を上げる!」という意思決定、つまり「粗利の意識改革」が高収益企業になるために絶対に不可欠だということです。
「値段が高いことは悪いことだ」という認識をあらため、「価格が高いということは付加価値が高いということだから顧客にとってもよいことだ」ということを全社員が腹落ちする必要があります。
短期的には売上は落ちますが、それを気にしては高収益企業にはなれません。「安いから買う」という顧客と訣別することは「高収益企業」になるための必要なステップです。
しっかり利益が取れる案件だけをやることのメリットはさまざまです。やっても儲からない案件がなくなることで、オペレーションがスッキリしますし、組織もスリム化できます。そして社員に高い報酬を払ってやることができるので、人の問題もかなり解消されます。そしてなにより顧客に感謝されます。これが一番のメリットです。
そんなシンプルかつ幸福を感じられる「高粗利経営」を実現させる第一歩は、経営者が「そうなる」と決めることから始まります。
