【経営革新コラム】 儲かるキラーサービスをつくる社長の視点 第279話:ぬるい組織を戦闘集団に変える方法
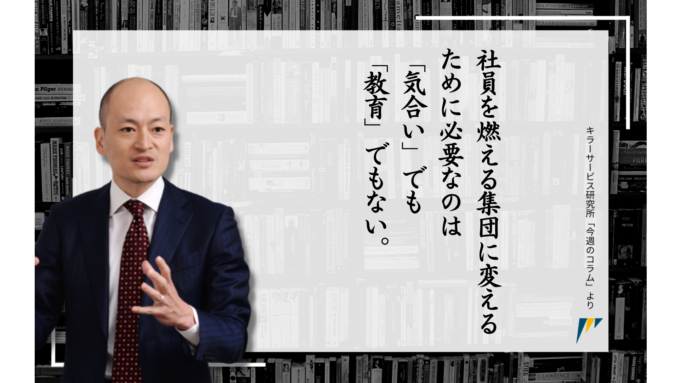
「うちの社員はほんとにぬるいなあ…」「ピリッとしないなあ…」と悩んでいる経営者は非常に多いと思います。
「同じ目標に向かって一致団結して頑張る組織集団」ーもしこんなものが市場で売られているとしたら経営者は借金してでも買いたいことでしょう。
ただ現実的にはそんなウルトラCは使えないため既存の社員をなんとかしようとするわけですが、動かない社員に対して「もっと覚悟を持て!」とか「危機感が足りない!」といった精神論をいくらぶつけても、経営者が思っている以上に効果はまったくありませんし、やるだけ無駄です。
それよりはちょっとマシですが大して効果が出ないのが「社員教育」です。できない社員を個々に教育しようとしても、そもそものやる気がなかったり、「現状で何が問題なの?」とか思っている社員になにを教えても実際の行動は変わりませんし、変わったとしても短期間で元に戻ります。
どんなに発破をかけても教育しても変わらない社員について思い悩む経営者の方は多いですが、私がそんな方々に常にお伝えしていることは「個々の社員に目を向けるのはやめましょう」ということです。
では何に目を向けるのかというと、そんな社員たちを取り巻く「構造」です。つまり、個々の社員を動かそうとするのではなく、彼らが動かざるを得ない構造(環境)をつくるということです。
具体的に必要になるのが「勝てる事業戦略」と「仕組み」です。
まず「事業戦略」ですが、個々の士気や能力よりも戦略の筋の良し悪しの方がよほど成果に直結することは、過去の戦や戦争の歴史が示しているとおりです。経営者によく読まれている「失敗の本質」などに詳しいですね。
ビジネスでいうと店舗ビジネスがわかりやすいでしょう。いくら店員がイキイキとしていて能力が高くても、商品や立地が悪かったらうまくいくはずがありません。
個々の社員の出来の悪さに嘆く前に事業コンセプトとポジショニング、商品力やマーケティング力、立地、セールスストーリーなどを整える方が先決です。
いつも言っている話ですが、地面を掘ったら金(きん)が出てくる場所に人を連れていけばやる気など勝手に出てくるものですし、逆も然りで成果が出にくい環境ではどんなに士気が高い人間もやがて腐ってくるものです。
2つ目の「仕組み」に関しても考え方は同じで、人に固執せずに環境を変えていきます。
仕組み化の基本は「仕事のやり方を事前に設計・標準化して誰でも一定水準の成果を出せるようにする」ということですが、他にもやれることはいろいろあります。
たとえば「営業マンの意識が低くて新規営業を全然やらない」という状況があるとすると、その営業マンを変えようとするより、テレアポ業者を使って死ぬほどアポを取らせて、営業マンが行かざるを得ない状況をつくるとか。
あるいは製造現場でミスが絶えないのであれば、原因究明と対策を徹底させることはやるとして、それでもだめならロボットで自動化したり外注に出したりしてミスが起こる工程自体をなくすとか。
このように戦略と仕組みを整えていくと、ボトルネックが解消されて事業の流れがでてきますので、気合いなどなくても社員は勝手にスピードを上げて動いていきます。
もちろん、それでも行動を変えない社員はいるでしょうが、プロジェクトマネジメントや評価制度といった仕組みをしっかり回せば、大抵の場合そういう人間は向こうから辞めていきます。
仕事ができる優秀な社長はこれまで自分という「個の力」に頼ってきたため、社員にやらせようとした時にも「個」に注視しがちですが、会社をスケールさせるためには「構造」に目を向ける全体視点とシステム思考が重要であり、そうして全体を整えることで結果的に個々の社員が活きてくることになります。
ここの順番が非常に大事ですので、なんか行き詰まっているなと感じるようでしたら、戦略づくりと仕組み化をガーっと一気にやってしまうことをお勧めします。
