【経営革新コラム】 儲かるキラーサービスをつくる社長の視点 第284話:事業成長に絶対に必要な「矛盾の解消」とは
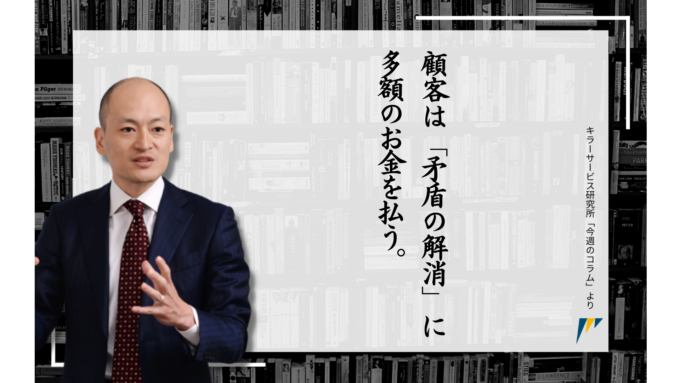
ビジネスで成功するためにはさまざまな「矛盾」と向き合う必要があります。以前の投稿でも書いた「感性と論理」や「ロマンとソロバン」もそうです。相反する概念を両方成り立たせることがビジネスを成立させるために不可欠となります。
当社が常々提唱している「特別化」と「標準化」の両立もまさに矛盾の解消です。
「特別化」とは一言でいうと「顧客にとって特別な存在となること」です。同業者がやっていないこと、できないことを提供することにより、値段を下げなくても選ばれる存在になることができます。
ここでわざわざ「差別化」ではなく「特別化」と言っているわけは、単に「差がある」というだけでは不十分だからです。
ビジネスも人がやる以上、同じような事業内容であっても会社ごとに個性は出ます。つまり「差」はつくられるわけですが、「差」があるからといって「もともと特別なオンリーワン」と言えるほどビジネスは甘い世界ではありません。同業他社とちょっと違う(ちょっといい)といった程度では意味がないのです。
競合が真似したくても簡単には真似できない強みを築くこと、それが「特別化」です。
一方、「標準化」というのは「どれも同じ」とか「均一」といった意味合いがあり「特別化」とは真逆の発想となりますが、これも事業の高収益化やスケール化にとってマストとなります。
この「標準化」というのは自社のビジネスプロセスにおいてできるだけイレギュラーを排除するアプローチになります。別の言い方をすると「ケースバイケース」や「場当たり的な対応」をできるだけ避けるということです。
具体的には、仕事の標準的なやり方・進め方をあらかじめ決めておき、フォーマットやチェックリストなどに落とし込んで複数の社員レベルで再現できるようにします。
この部分をおろそかにすると、一部のできる社員(社長含む)ばかりに仕事が集まったり、あるいは社内で起きるミスやクレームの対処ばかりに追われて肝心な重要なテーマにいつまでたっても手をつけられないという状態になります。
人には得意不得意がありますから、経営者の個性が影響してどちらかの要素に偏りが出るものです。苦手な方、手薄な方を集中してテコ入れすると事業はガラッとよくなることも多いですし、さらに強みを伸ばしていく余裕も生まれます。
一番避けたいのが「どっちも中途半端」という状態です。これはいくらバランスが良くても企業の競争力という点では危険です。大谷選手が二刀流と讃えられるのは投打どちらも一流だからであって、二軍レベルで二刀流をやっても話題にはならないはずです。
いまうちの会社はどちらに傾いているのか、あるいは低位安定していないか…まずは経営者が自社の現状を把握することが大切です。
事業を高収益化するために「特別化」と「標準化」、どちらも極めていきましょう。
