【経営革新コラム】 儲かるキラーサービスをつくる社長の視点 第140話:業績上げたければ、売ってはいけない3つのもの
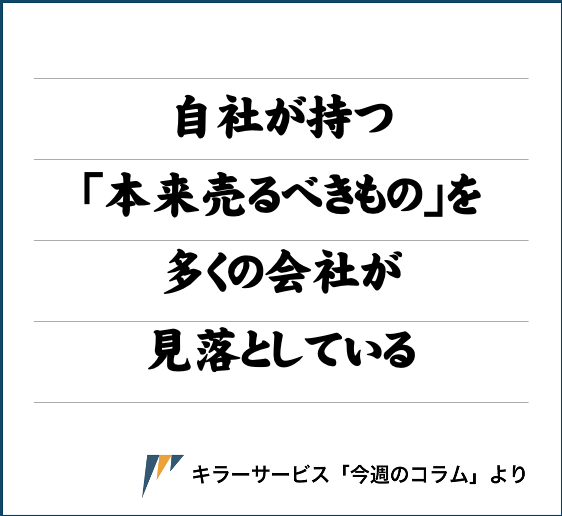
「なるほどー、ずっと悩んでいましたが、これで売上も利益も上げられるイメージが湧きました!」―― 先日スポットでのご相談に見えた社長の方が、晴れ晴れした顔でそうおっしゃいました」
この社長は、業界が深刻な人手不足に見舞われていることもあり、「とにかく人を雇わないといけない!」という意識で長年やってこられたものの、その先の事業飛躍の筋書きが書けないとお悩みでした。
この社長に限らず、事業の業績が伸び悩む方の多くは「ある思考」に捉われていることが非常に多いと感じます。
その思考とは、ある「売ってはいけない3つのもの」を売ろうとする思考なのですが、それはなにかというと、
「モノ」
「手間」
「時間」
の3つです。以下、ひとつずつご説明します。
まず「モノ」というのは、(有形の)商品ということになりますが、これは「商品を売ってはいけない」ということではありません。当社は社名が「キラーサービス研究所」というだけあって「(商品を売らない)サービス業」となることを推奨しているように思われがちですが、これは全くの誤解です。
「モノを売ってはいけない」というのは、正確にお伝えすると「単にモノを売ってその対価をもらうという発想だと儲かりませんよ」という意味です。
なぜ単にモノを売る発想ではいけないかというと、その答えは単純で、その商品がよほど特異なものでない限り、商品単体での差別化が難しいからです。
もちろん、世の中には商品の特異性でちゃんと成り立っている企業もあります。ダイソンなんてまさに商品のユニークさで勝負していますし、和製ダイソンとの異名も高いバリュミューダという会社も非常に面白い家電製品で人気を保っています。
しかしながら、基本的にモノが有り余っている今の時代において、ヒット商品を出し続けるというのは、リソース(人手や資金)に限りがある中小企業の戦略としては非常にハードルが高いです。
他社製品よりも性能やデザインが少しいいというレベルでは、結局市場の価格相場に引っ張られ、業績も「業界なり」となってしまうというパターンが圧倒的です。
現に「モノだけを売っても難しい時代」だからこそ、いま「サブスク」がブームとなっているといえます。このサブスクというのはよく「月額課金制」との説明がなされていますが、実は単に課金方法を一括から月額にすることがサブスクではまったくなく、モノ+α(アルファ)を提供するために最適だから月額課金にしているというのが本質です。
実際はこの本質を理解しておらず、最初にモノを提供して、あとはずっと特に何もせずにただ課金だけ続けている「ダメなサブスク」をやってしまって行き詰まっている企業も多いですが、サブスクにせよ何にせよ、モノだけを提供する発想を変えていかないと、ビジネスの広がりは期待できない時代となっています。
ではサービス業ならいいのかというと、これもそうではありません。多くのサービス業が、先ほど挙げた「手間」や「時間」を売る発想に陥り、業績が頭打ちになってしまっています。
「手間」を売るというのは、他社よりも手間をかけたサービスを提供する(これはモノを売る場合も含めて)ということですが、手間をかけるというのは「作業を提供する」発想となります。
「うちは他者と違ってここまでやっていますよ」というアピールにはなるかもしれませんが、それが単なる作業ということであれば、もらえるのは当然ながら「追加の作業賃」となりますから、ビジネス的には大して旨味はなく、実際は現場が疲弊して続かないということにもなりかねません。
これは「時間」も同じことで、提供しているサービスが基本的には人が手足を動かす「作業」にとどまるのであれば、いただける代金は基本的には「作業賃」になってしまうということになります。
これも「モノ」のところで言及したとおり、手間や時間を提供してはいけないということではなく、手間や時間『だけ』を提供する発想だとビジネスは頭打ちするということです。
これは言ってみれば当たり前の話で、人が手を動かせる体力や時間には当然限りがあるわけですし、これを機械化・自動化したところで、それは他社も遅かれ早かれやっていうでしょうから、単に作業を機械化しただけでは付加価値とはなりません。
では何を売ればいいのかということですが、これは明確で、売るべきものは『知恵』ということになります。
他社では提供していない、独自の『知恵』を通常の商品やサービスに付加することができれば、ビジネスは飛躍的に面白くなってきます。
たとえば「手間」を提供する場合においても、その手間をかけるオペレーションを標準化し、仕組みで効率よく廻せるようにすれば、お客様には「手間暇かけたサービス」を提供しながらも、自社の現場オペレーションは大した負荷がかかっておらず、そのギャップを付加価値に変えることができます。
あるいは、商品やサービスを提供する際に、お客様では知りえない「ノウハウ」や「知見」を提供することができれば、お客様の体験は特別なものになる可能性があります。
そういうと「うちにはそんな特別な知見やノウハウはない」と思われるかもしれませんが、これは当社が様々な会社と「特別ビジネス」をつくってきた経験上言えることですが、あるご商売を一定期間継続されてきた会社には、自分たちにとっては「当たり前」と思っていることでも、お客様にとっては「特別」となる知恵が、その現場には必ず落ちているのです。
その「知恵」をちゃんと見えるカタチにして提供できれば、それは「粗利100%」の高付加価値な無形商品となります。そしてそういったアナログな知恵は、このデジタル時代において「簡単にまねできないもの」として際立ち御社を輝かせます。
御社は「作業」を提供して物理的限界にぶつかっていませんか?
現場に存在する「知恵」を見える化し、現状のビジネスを格上げしていきましょう。
