【経営革新コラム】 儲かるキラーサービスをつくる社長の視点 第268話:中小企業の社長が自らつくっている「成長の限界」
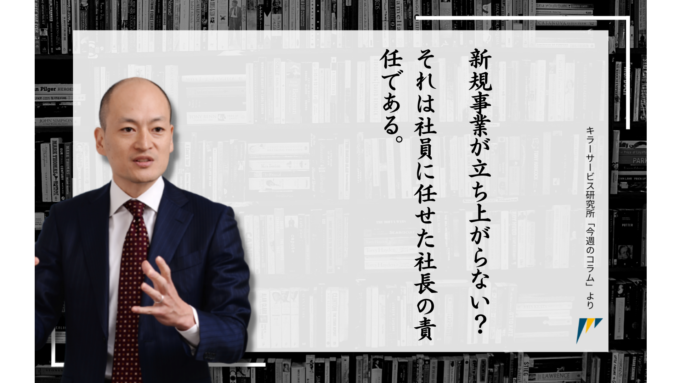
どんなにいい事業をやっていても、いつか陳腐化するのは当然のことです。どんなにうまくやっていてもいつかは競合に真似されますし、それに世の中の情勢や顧客ニーズもどんどん変わっていきます。そしてその変化のサイクルもどんどん短くなっています。
そんなことは経営者であれば当然おわかりでしょうし、新しい事業の立ち上げや新商品・サービス開発を検討中の企業も多いことでしょう。
当社にコンサルティングをご依頼になる企業も基本的には経営者が上記のように「新しい事業の柱」をつくりたいと考えて始められるケースがほとんどです。
企業によって当然差はありますが、平均して2〜3ヶ月かけていろんなアイデアを検討し、そして新しい事業や商品・サービス内容の骨子が固まります。
この段階で経営者はホッとされます。もちろんここからさらに具体的な検討を重ねる必要は当然ありますが、まずは自社が進むべき新しい道が見えたことに安堵されます。
そして、ここからの進捗スピードは企業によって大きく差が出ます。社長と幹部がどんどん議論をしてスピーディーに事業モデルの具現化を実現する企業もあれば、反対に具体的な検討が一向に進まない企業もときに出現します。
前者の企業では経営者もそうですが、特に実行部隊である部課長が前のめりです。当然現業も忙しいでしょうことでしょうが、早くその新しいことをやりたいと精力的に検討の時間を使われます。その時間を捻出するために、いまやっている仕事の効率化も同時に進めるところも出てきます。非常にポジティブなエネルギーが推進力となっています。
一方で後者の企業は上記の真逆です。少なくとも経営者はやる必要性を感じていますが、幹部社員の方はそうでもありません。ただでさえ忙しいのに、さらに新しいことをやれって言われてもなあ…という感じでしょう。
中でも進まないパターンは、社長が検討を部課長に丸投げするパターンです。「コンサルの先生を連れてきたから、あとは先生とお前たちで考えろ」なんて言われたら社員はたまったもんじゃありません。(まあそこまでひどい言い方ではないと思いますが…)
社長の言い分としては「実行部隊である彼らがやる気にならなかったらそもそも進まないんだから、最初の検討から彼ら中心にやらしている」というものが多いのですが、果たしてそうでしょうか。
新規事業を立ち上げるにあたって一番重要なことは、言うまでもなく「事業性の判断」、つまり筋の良し悪しです。新しい事業が当たるかどうかはやってみないとわからないとはいえ、少なくとも経営の責任者である社長が「これはいけそう」「儲かりそう」と思えるものでないと進められません。
そして、この判断を社員にやらせるのは大いなる過ちです。なぜなら社員はいくつかの理由から正しい判断が下せないからです。
まずは能力の問題です。社員というのは管理書であっても基本的には上からやれと言われたことを愚直にやって評価されてきた人材です。そんな人材にいきなり新事業の事業性を見極めろといっても無理があります。普段の仕事の実行力と、未知なる事業についての判断力はまったく異なる能力です。
さらに、「責任が大きすぎる」という問題があります。新規事業に失敗したときに社員では責任が取れません。社長が「責任は俺が取る」と言ったところで実際はそうはならないことは社員はわかっていますから、リスクを考えるとどうしてもGOかNO GOかでいうとどうしてもNO GOの方に気持ちが傾きます。
そして、一番問題なのが、社員に判断させたら「自分たちでできるかどうか」という判断軸で考えがちということです。自分たちのこれまでの経験や現在のキャパを考えると、「やっぱり今は無理」という結論になりがちです。
そして社長も「やっぱりそうかあ、難いかあ…」となったりするわけですが、これは自社の成長の限界を「既存社員の能力」で決めてしまっていることになります。
社長は、今の社員でできるかどうかは一旦横においておき、純粋に事業性を判断する必要があります。そして、「この事業はやるべき」と判断したならば、あとは誰にどうやらせるかと考えるのが正しい順番です。
このときに、必ずしも自社に適任者がいるとは限りません。というか中小企業の場合は適任者などいない確率の方が高いでしょう。いないなら連れてくるしかありません。そして、その方がうまくいく可能性は高いです。わざわざやる気もなく能力もミスマッチである既存社員を無理して起用する必要はないのです。
「事業機会があるから人を雇う」と考えるか、「人がいないから事業機会を見送る」と考えるか。この違いが企業の明暗を分けます。いずれにしても判断を下すのは社員ではなく社長の仕事です。
