【経営革新コラム】 儲かるキラーサービスをつくる社長の視点 第270回:材料費・電気代・人件費高騰時代の経営の考え方
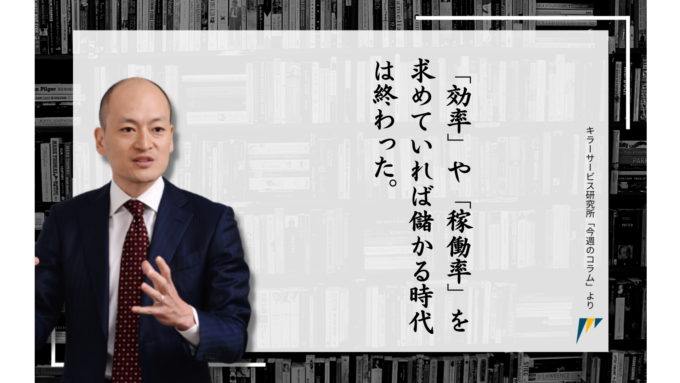
「うちの電気代、月3、40万円だったのが先月はなんと100万円ですよ…」── 製造業を営むM社長の口から悲痛の声がこぼれます。
ここ数年続く木材や金属などの材料高騰に加えて、電気代をはじめとする光熱費も大幅に上昇。製造業にとっては大きな痛手です。
加えて人件費も上がってきています。正確には「上げないと人材が採れない」という状況になりつつあります。ユニクロが初任給を25万円から30万円に引き上げると先日発表しましたが、他の大手も今後追随していくことでしょう。
電気代の高騰はウクライナ戦争という特別要因が大きく関係していますが、材料費と人件費の高騰は、それぞれ「資源不足」「労働力不足」という構造的な問題に起因していますので、この先も基本的には高止まりするでしょう。特に人件費についてはこの先もう一段上がっていくようにも思えます。
つまり、経営者は今後「高材料費、高人件費」をベースに事業を組み立てる必要があるということになります。
そうなると、経営者の仕事、求められる役割がこれまでと大きく変わってくることに経営者は気づく必要があります。
これまで多くの経営者が追求してきたことは「効率」や「稼働率」です。社員や機械設備をいかに遊ばせずに動かすか。社員や機械を「隙間なく稼働させる」ことに意識を向けてきたことでしょう。
しかしこれからは、単に社員や機械が「稼働している」だけでは不十分となります。これからの時代、経営者が追い求めるべきものは「付加価値」です。社員や機械設備の稼働によってどのような「付加価値」を生み出せるかが経営の鍵になってくるということです。
この変化は経営者に求められることが従来より非常に高度化することを意味しています。なぜなら、社員がサボらないように動機付けするよりも、彼らが高い付加価値を生み出すように導くことの方がよほど知恵が必要だからです。
会社を高付加価値企業に変化させる切り口はいくつもありますが、一番基本的な考え方は「単なる作業の提供をやめる」ということです。
社員がせっせと手を動かして作業をする。この労働の対価は「作業賃」となります。作業賃をもらうだけのビジネスでは豊かになることができません。価格決定権を握ることができず、他社と同様の価格しか通らないからです。
では何を提供すればいいのか。それは一言でいうと「知恵」です。作業をするために手足を動かすのではなく、知恵を絞るのです。顧客にはない自社独自の「知恵」を活かした商品・サービスを提供することができれば、作業代行よりもはるかに高い付加価値を顧客に提供することができます。
もちろんこれは、経営者が社員に対して「作業をするな、もっと知恵を絞れ!」と発破をかけて実現できるものではありません。そのような個人任せの知恵の提供ではなく、標準化されたサービスとして価値をつくる必要があります。
うまく行っているビジネスというのは、通常のよくあるビジネスにひとひねり加えて絶妙に「知恵」を効かせているものです。
たとえば、あるコインランドリーでは店員が常駐していて、洗濯物を預かってくれて洗濯しておいてくれます。
「え? それって単なる作業代行じゃないの?」と思われるかもしれませんが、そうではないんですね。その店員は「クリーニング師」という資格を持っていて、簡単に言うと「洗濯のことをよくわかっている人」なのです。
そんな店員さんに洗濯を任せることによって、
・終わったらLINEで連絡をくれるので、店で待たなくていい
・当日取りに行けなくてもしばらく預かってくれる
・最適な洗濯時間・乾燥時間を設定してくれるので、お金を入れすぎることがない
・ふとんの乾燥は途中で裏返してくれて乾燥ムラがなくふっくら仕上がる
といったメリットがあり非常に顧客満足度が高くなっています。またお店の方も店員を置くことで機械の稼働率が上がり収益性が格段に高まるとのこと。
これはほんの一例ですが、世の中を見渡すと「知恵」を効かせて自社事業を儲かるビジネスに仕立てている例はたくさんあります。
いまや、社員がせっせと真面目に仕事をすれば儲かるという時代ではありません。いかに「違う視点を持つか」という勝負になってきているということです。
御社は「自社ならではの視点」でユニークな価値を顧客に提供できていますか? 作業代行で疲弊していませんか?
「知恵」を効かせた高収益・高付加価値ビジネスを構築し、資材や人件費が上がっても利益が出る体質をつくっていきましょう。
