【経営革新コラム】 儲かるキラーサービスをつくる社長の視点 第280話:中小企業が三流社員を使って儲ける方法
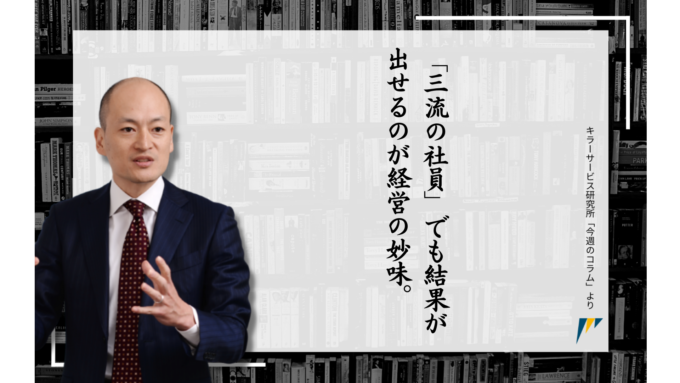
「中小企業は社員のレベルが低いから社員教育はマストでしょう。三流社員はなんとか教育して、せめて二流レベルに育てないと…!」── 前回のコラムをお読みいただいた経営者の方がこうおっしゃいました。
雇った社員がろくに成果を出さない現実を前にして上記のようにお考えになる気持ちはわかるのですが、実際にはこの逆の発想が必要です。
つまり「三流社員でも結果が出せるビジネス」をつくる必要があるということです。
極端なことを言っているように聞こえるかもしれませんが、中小企業にとってはこれが極めて現実的な考え方だと思います。
まず「一流社員」に関しては、中小企業にそんな人材はまず入ってこないですし、万が一入ってきてもその人しかできない仕事が発生する(=属人化・スケールしない)か、あるいは朱に交わってやがて二流になっていくかのどちらかです。
ですから、中小零細においては「二流社員」こそが二八の法則でいう二割の優秀な社員ということになります。そして、残り八割の三流社員を教育によって二流に育てるというのは非常にコストと時間がかかりますし、やったとしても八割の二割(つまり16%)ぐらいしか育たないでしょう。三流を二流にするというのは言うほど簡単ではないのです。
それよりも優先順位としては「人」以外のところから最適化していく方がよほどコスパが高いです。
たとえば複数の営業マンを抱えている会社で「一部の人間しか売ってこない」というのはよくある現象ですが、この場合は営業マンを教育するより商品やサービスをもっと売りやすいものに変える方が効果的です。
売りにくい商品の例の代表格が、顧客のニーズに合わせた「完全特注品」です。たとえば工場で使う高額な特注設備などは、そもそも顧客のニーズを聞き出せるぐらいの関係性を構築する必要がありますし、そのニーズを的確に掴んで最適な提案をするなんてことは一部の優秀な人間にしか不可能です。
何十万もするオーダースーツなども同様で、すでに頼んでいるところがあって満足しているとしたら普通は業者は変えません。失敗したくないからです。
このような場合は、あらかじめ仕様や価格が決まっている標準品か半標準(セミカスタマイズ)品を用意することで格段に売りやすくなりますし、マーケティングによる新規開拓も可能になります。
加えて「発注前の専門家による無料カウンセリング」や「超特急納期」、あるいは「納品後の修正無制限」といった特別サービスをあらかじめオファーすることができればさらに受注のハードルを下げることができます。
もちろん、このような商品・サービスの標準化や特別対応の企画および仕組み化を実現するためには社員の努力が必要になるわけですが、「社員教育」という漠然とした取り組みよりもはるかに目的や実施内容が具体的ではっきりしているため実行しやすく、かつ成果もでやすくなります。
「勝敗は戦う前に決する」とは兵法における定石ですが、事業においての勝ち負けも「社員側」ではなく「経営側」での企画段階で概ね決まるものであり、そこがうまく行けば「普通の社員」でも大きな成果を出すことが可能で、多くの経営者が抱える「社員についての悩み」も減ってくることになります。
