【経営革新コラム】 儲かるキラーサービスをつくる社長の視点 第174話:業績悪化にすぐに対処する会社が見落としていること
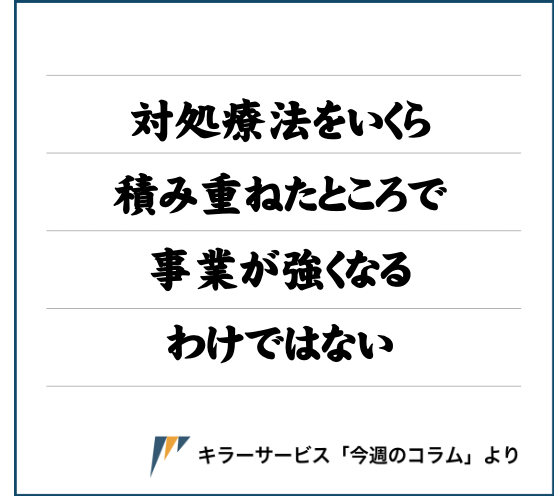
「いよいよ売上が落ち込んできました。時間差でコロナの影響が出てきたみたいです。今回ばかりは今までのような対処では難しい気がしていまして…」
以前当社のセミナーにオンラインで参加された社長がご相談に来られました。「いよいようちの業界も…」と悲痛な面持ちをされています。
「売上が落ちてきたときに、売上を上げようとしたらいけないんです」とお伝えすると、「え? じゃあどうしろと言うんです?」と続きを待たれました。
コロナ禍の経済への影響は今後多方面な業界に広がっていく可能性があります。飲食や観光業だけの問題ではありません。人が巣篭もりして経済を回さなければ、そのしっぺ返しは当然ながら全体の経済に対して向かいます。
「資金繰りが苦しくなってきた」といって融資に走る人も増えるでしょう。「売上が下がってきた」といって営業やマーケティングを強化する人も増えるでしょう。
顕著化した業績悪化に対して迅速に対処する必要があることはもちろんそうなのですが、「業績が悪化したらすぐに対処」という行動の裏には、実は根深い問題が潜んでいる場合があります。
それは、文字通り「対処療法で済ます」というマインド(思考の癖)に経営者が陥っているということです。
よく商売は魚釣りに例えられます。海釣りでいうと、「潮を読んでちゃんと魚が泳いでいるところを選び、かつ適切なルアーを垂らす」という単純なことができていないと、魚は釣れませんよという話です。
潮の流れは必ず変わりますから、漁師でしたら漁船に魚群探知機がついており、常に魚のいる場所をさぐってそこに向かいます。また、その時期にその場所だとどんな魚が泳いでいて、その魚はどんなルアーに食いつくかということも漁師は分かっていますから、海に魚さえいてくれれば漁師は漁を成立させることができます。
しかしながら、これが商売に関していえば少々話が違ってきます。
まずはじめに、商売においても魚釣りと同様に潮の流れは必ず変わり、同じ場所で同じことをやっていたらやがてお客様はいなくなってしまうのですが、そのことから目を背けている経営者が多いのです。
その結果、業績悪化という現象を「自社に降ってかかった不運」のように捉えて、慌てふためきながら対処するということになります。
確かにリーマンショックや今回のコロナ禍はその「陳腐化」の動きを大きく加速させるものではありますが、そういった外部環境の変化というものも、海で言うと台風による大荒れが必ず毎年くるようなもので、一定の期間を開けて必ずくるものです。
そして、そういった外部環境のネガティブな変化が来てからあわてて対処する経営者の場合、その備えができておらず、かつ時間的な猶予も限られるため、「下がった売上を短期に上げる(回復させる)ための手段」しか選べないということになりがちです。
何が言いたいかといいますと、業績を継続的に伸ばしている経営者であれば、「いずれはいろいろと問題が起きる」と考えて、商売が好調な間に手を講じるということです。
『このまま順調に伸びたら社内がパンクするから、いまのうちに自動化の仕組みを作っておこう』
『いまの少数の顧客に頼っているのはリスクがあるから、いまのうちに違う業界にも販路ができるように動こう』
『いまは好調だけど、いつか必ず競合に真似されるから、今のうちに新しい切り口を考えてテストをはじめていこう』
そのように「早め、早め」に考えて手を打つ。そのような時間的余裕をもって動く経営者に何が得られるか。それはは「全体的視野」です。対処療法ではない、「事業を強くする根本的な一手」を選ぶことができるということです。
この「根本的な一手」を打てているか── ここが事業を継続的に伸ばしていけるか、それとも市況の流れに左右されて常に一喜一憂するかの分かれ道となります。
当社が「特別ビジネスの構築」をご支援している理由もここにあります。企業が成長していくためには、販売手法や組織運営の方法といった、いわゆる「部分最適化」だけをやっていてもしょうがないと考え、そもそもの『事業コンセプト』を強くするためのアプローチにこだわっています。「根本的な一手」を講じるお手伝いをすることが当社の役目です。
魚がどこにいるのかとあちこち探ってみたり、魚が集まるように集客の手段を講じたりしても、肝心のルアーが「魚に刺さるもの」でなかったら何の意味もありません。
御社では自らの事業を「とがらせる」ための取り組みはちゃんと機能していますか? 目先の魚を釣り上げることに意識のすべてが向かっていませんか?
新しい仕掛けを海に投げ込むことこそ、経営の醍醐味であると当社は考えています。
