【経営革新コラム】 儲かるキラーサービスをつくる社長の視点 第209話:好調な企業が打ち出す「共感ストーリー」とは
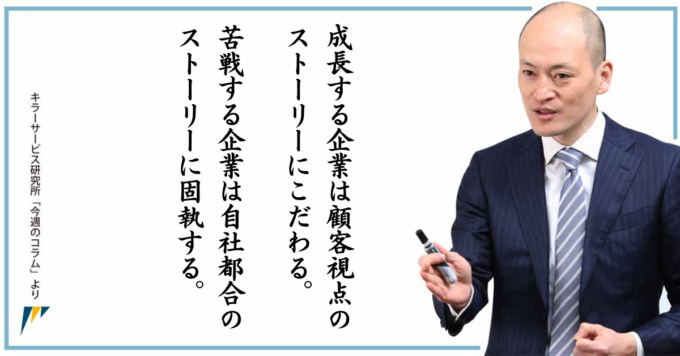
「やっぱりPB(プライベートブランド)をしっかり開発しているところは強いですねえ」── スーパーマーケット業を営むクライアント先のH社長に、無印良品が打ち出した大幅値下げについて話を振ったときに出たお言葉です。
同社も現在自社ブランドの確立に取り組まれていますが、企業ブランドをつくる上でも、利益率を確保する上でも自社商品・PB品の開発はマストだというわけです。
実際、西友のPB品としてスタートした無印良品は、その名のとおり「飾らないシンプルな商品づくり」というぶれない軸を守り続けて、いまや揺るぎないブランディングを確率しました。
同社は商品づくりにおいて「3つの視点」にこだわっています。それは、①素材の選択、②工程の点検、③包装の簡略化、というものです。これらを継続して追求する視点の先には、常に「顧客のために」という、それこそシンプルで実質本位な思いが込められています。
その思いが、冒頭の同社の値下げにも現れています。
コロナによる稼働停滞や天候悪化などに起因して値上げを打ち出す企業も多い中で、巣ごもり需要で販売好調な同社がわざわざ値下げをする必要はなかったように見えます。
しかし、彼らの言い分はとてもシンプルです。「販売が伸びてコストが下がったし、複数商品の材料の共通化などでもコストが下がったので、値下げします」と。
このメッセージには、「販売を増やすため」とか「ライバル企業を出し抜くため」といったよくある値下げにはない、企業にとって非常に重要なあるものが含まれています。
それは『共感ストーリー』です。
共感ストーリーとは、それを聞いた顧客が「やっぱりこの会社はいいなあ〜」と思ってしまうような、顧客に寄り添う考え方や姿勢のことを指します。
「売るために値引きする」のではなく「売れたから値引きする(お返しする)」── この姿勢が顧客の共感を生み、結局は「値段とかではなく無印だから買う」という指名買いの顧客を増やすことになります。
業績好調が続く企業は漏れなくこの「共感ストーリー」を軸にした事業活動を展開しています。
たとえば、PBといえば「プライベートブランドの革命児」と言われたのがセブンイレブンですが、ここも「セブンプレミアム」の展開にあたり、従来のPBの概念を覆すような共感ストーリーを打ち出しました。
当時のPBといえば「安かろう悪かろう」というイメージだったわけですが、セブンプレミアムでは本当の顧客満足を実現すべく、「高品質で安全・安心」にこだわる方針を取ったのです。
さらには、「PBなのに安くない」というだけでも異例であるところに、「顧客に安心していただくため」ということで共同開発のメーカー名を商品に明記したのです。これはいまでは他社も追随していますが、当時はかなり話題となりました。
「顧客のために徹底的に品質にこだわる」という同社の一貫した姿勢はライバル企業と完全に一線を画し、コンビニ界で圧倒的な地位を確立することになりました。
もちろん、「共感ストーリー」を打ち出して成功している企業は大企業に限りません。中小企業においても独自のストーリーに基づいた事業展開で大きく業績を伸ばしているところが数多くあります。
たとえば「すごい工場」という書籍でも紹介されている鋼材加工会社スチールテック。同社の工場はかつて、よくある鋼材加工の工場と同じく粉塵まみれの油まみれ、通路にも「商品」たる鋼材が雑然と置かれ、その上を作業員が土足で歩く…そのような状態でした。
そのような中、2代目の出口社長は、「もっと社員が働きやすい環境をつくってやろう」と一念発起し、ショールームのようなピカピカの新工場を建設します。
この「工場のショールーム化」に社員たちが喜ばないはずがありません。この環境を維持しようと全社で「環境整備」という取り組みを継続し、いつでもピッカピカな工場とオフィスが保たれています。
そして、喜んだのは同社の社員たちだけではありません。工場見学に来た新規顧客の8割が、その有り得ないぐらいピカピカな工場とニコニコと笑顔で挨拶する社員たちの姿を見て感動して、見積もりもそこそこに同社に発注していくといいます。
同社のような加工業においてはQCD(品質・価格・納期)で勝負する会社がほとんどですが、スチールテックの場合は、その「環境」に共感した顧客がある意味勝手に「ここは競争力があるはずだ」と判断して発注してくれるというわけです。
他にも例をあげればキリがありませんが、顧客が満足して指名買いをするような会社においては、必ずと言っていいほど経営者や社員の思いが独自のストーリーとなっています。
当社のコンサルティングにおいても、クライアント企業独自のキラーサービスをつくる上で非常に初期の段階からこの「共感ストーリー」の明確化に力を注ぎます。なぜなら、そこが甘いと後でどのような施策を打っても意味をなさないからです。
御社では顧客に指名買いされるような独自のストーリーは明確になっていますか? 皆さんの想いは顧客に届くカタチになっていますか?
